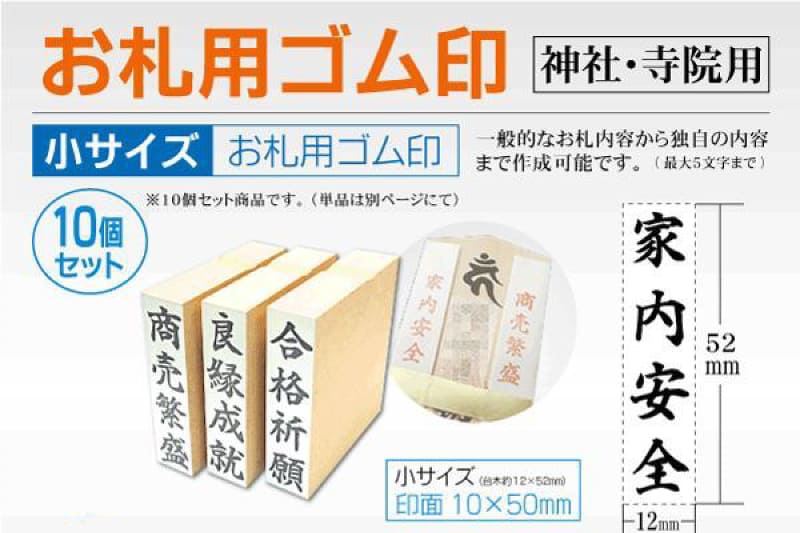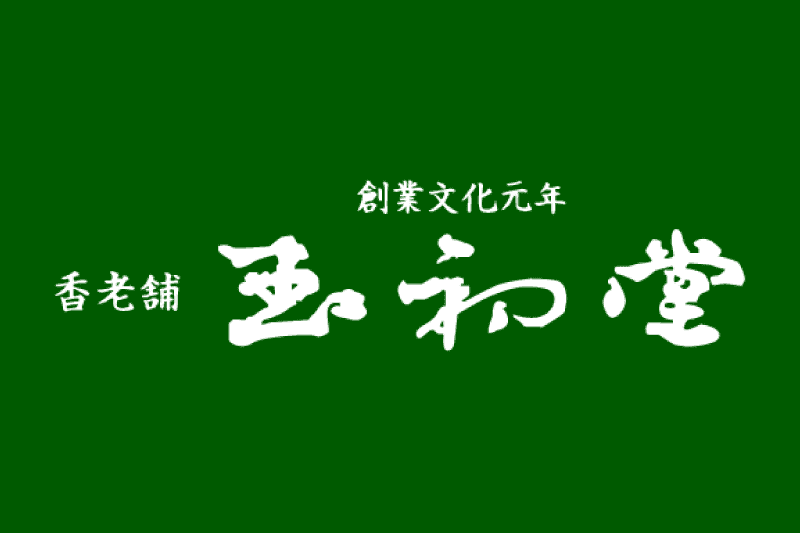超詳しい護摩札のおはなし~その6~護摩札の正しい置き場所

こんにちは「卒塔婆屋さん」代表の谷治です。昨日は護摩札のサイズや材質についてお話しました。本日は護摩札の置き場所について解説します。
目次
護摩札の置き場所
お護摩の加持祈祷をしてもらったあと、護摩札をいただくことがあります。
慣れている人であれば大丈夫ですが、初めて貰う人にとっては、その置き場所一つでも頭を悩ませてしまうもの。
護摩祈祷で護摩札をもらったら、次はそれを置く場所をしっかりと設けましょう。護摩札には不動明王の分霊や力が宿っているため、机の上や引き出しのなかにしまったり、おざなりに扱ったりしてはいけません。
粗末にしないよう、また護摩札を家庭内で敬うご本尊さまとして大切にお迎えし、日々自分自身の祈りを深め感謝の気持ちを表せるとよいですね。
ここでは、護摩札の置き場所の例をいくつかご紹介します。
護摩札を不動明王そのものとしてお祀りすることで、日々心の幅を広げるように心がけてくださいね。
神棚があれば神棚へ
護摩札は、自宅やオフィスなどに神棚があれば、その神棚へ置くとよいでしょう。
神棚とは、神様をお祀りする神聖で清らかな場所のこと。自宅では、神社や寺院でいただいた神札や護符、お守りや破魔矢などをお祀りする場所として使います。
神棚では、いただいたものを祀るほかに、神社や寺院で神様・仏様をお参りするのと同じように、感謝を示したり祈祷したりすることができます。
定期的に寺院や神社に行けなくても、神棚に向かって毎日手を合わせること。それで神様・仏様に見守っていただき、諸願成就を祈るための「つながり」の場。そこは不動明王の分霊や力が宿る護摩札を置くのにも最適です。
近年では、従来の和づくりで豪華なもののほかに、洋風の間取りにも合うシンプルかつモダンな神棚も販売されています。そのほかに、お札を祀るための神棚やお札額なども売っています。もし「自宅に神棚はないけれど、これを機に設置したい」とお考えの方は、「モダン神棚」や「お札立て」などで検索してみると、好みのものが見つかるかもしれません。
神棚がないとき
近年では、神棚のない家が増えています。その場合でも安心してください。大切なのは、神棚に飾るかどうかではなく、真心や感謝の気持ちを持ち、丁寧に祀ることなのです。
そして正しく祈りを捧げるために、飾るのに最適な向きと高さがあることをしておくとよいでしょう。
その正しい向きと高さとは、下記のとおりです。
・字の書いてある面を表向きにすること。
・オモテ面を南向きか東向きにすること。
・お手洗いなどの不浄な場所は避けること。
・人通りの多い玄関は避けること。
・絶対に画鋲を使用ないこと。
何度も繰り返すように、護摩は密教において大切な儀式であり、護摩札は仏様のご分身です。そのため、仏様が「嫌」だと思わなさそうな、よい場所に配置することを忘れてはいけないのです。
以上の注意点を踏まえれば、壁や家具の上に置いても構いません。
護摩札を置くときの注意点
護摩札を置くときは、「清潔」で、「良好な環境」の場所に置くことがもっとも大切です。
具体的には人の目線よりも高く、清潔な場所が推奨されています。神棚がなく、箪笥などの背が高い家具の上に置く場合は、かならず置き場所を綺麗に掃除すること。そこが神聖な空間であることを示すために、白い布を引いておくとよりよい環境となります。飾ったあとは、定期的に掃除をしてホコリやゴミを取り除きましょう。そのほか背の高い家具がないときは、壁や柱にテープで貼り付けても構いません。画鋲を使うことは厳禁ですが、両面テープ等で貼り付けるのは大丈夫です。
不安定なまま祀ると、不意に落下する可能性があり、非常に縁起が悪いです。安定させるために両面テープや札立てを用いたほうがよいということです。
神棚のほかに、家具屋や雑貨屋で売っているようなラックを設置するのも一つの方法です。
仏様の護摩札ですから、仏壇があれば仏壇に置くのもよいでしょう。
会社で護摩札を飾るときの注意点
また、護摩札を会社や事務所に設置する人も多いでしょう。
職場の場合も、基本的に家と飾り方は同じです。明るく清らかな場所で、人が集まる場所や業務の中心となる場所に飾れると効果的です。
また、神棚に背を向けることはあまりよいこととされていませんが、どうしても机の位置関係で、全員が全員守れるわけではありませんよね。それは仕方ないことですので、その場合は気にしすぎる必要はありません。対処方法として、神棚を人の目線よりも上に配置することが望ましいです。
そのほかの注意点として、基本的に私たちが神棚の下を通るのはあまり推奨されません。そのため出入り口など、人の通りが多い場所に設置するのは避けましょう。
そのほか神棚を置く場所が、その家屋の最上階でない場合。その場合に効果的な対象方法として、神棚の上に「雲」と書かれた紙を貼ることをおすすめします。そうすると「ここが一番高い場所ですよ」という意味になるのです。
また、住まいの都合により、上記のようにお祀りすることが困難な場合は、自分が祈願しやすい場所や、家族・社員全員がそろってご祈願しやすい場所に置くとよいでしょう。
お寺の護摩札は神棚に置いてもよい
神棚というと、「神」と付いていますし、寺院でいただける護摩札を一緒に飾ってしまってもいいのか、たびたび議論になりますよね。人によっては、駄目だという人もいますし、明治以前の神仏習合の名残から、あまり気にしないという人もいます。
実際のところ、結論から言ってしまいますと、お寺で貰ったお札は神棚に置いて構いませんし、自身の判断に寄るところが大いにあります。
しかし神社でいただいたお札などと一緒に飾る際は、注意が必要です。お寺のお札と神社のお札を一緒に祀る場合は、それらを重ねて置かないように注意しましょう。片方をおざなりにしたり、ぞんざいに扱ったりするのは推奨されません。
なぜ東向きか西向き?
上記で、護摩札は置く場所のほかに、方角合わせも大切だと記しました。その通り、護符や護摩札は基本的に東向きか西向きに祀ることが推奨されていますが、その理由をご存知でしょうか?
その理由は、太陽は東から上り、日中は南に太陽が輝くからです。
そのため東や南の壁に貼るのではなく、北や西に貼り、表面(字が書いてある面)を東や南に向けるのが正しいことになります。
意外と分かっているようで分かっていない、いざ、置こうとしてもどうして良いか分からないことについて解説しました。明日は護摩札の祀り方についてお話します。
この記事を書いた人
DAISUKE YAJI
プロフィール
1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業
1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社
2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社
2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社
2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任
2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)
2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞
2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞
2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞
義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯
趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

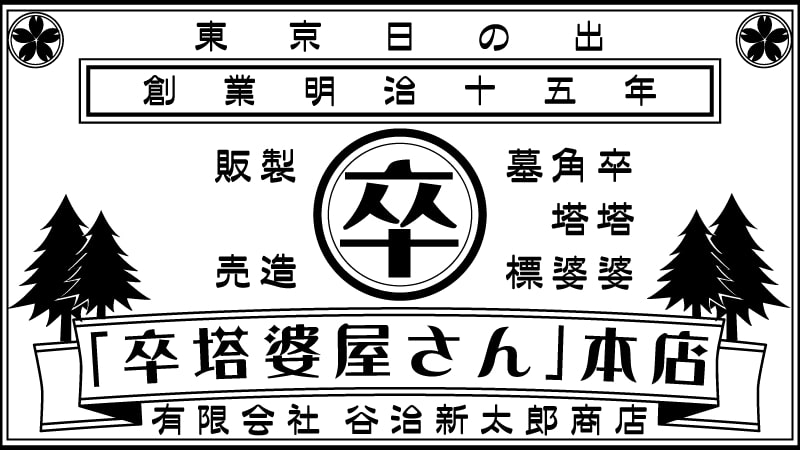








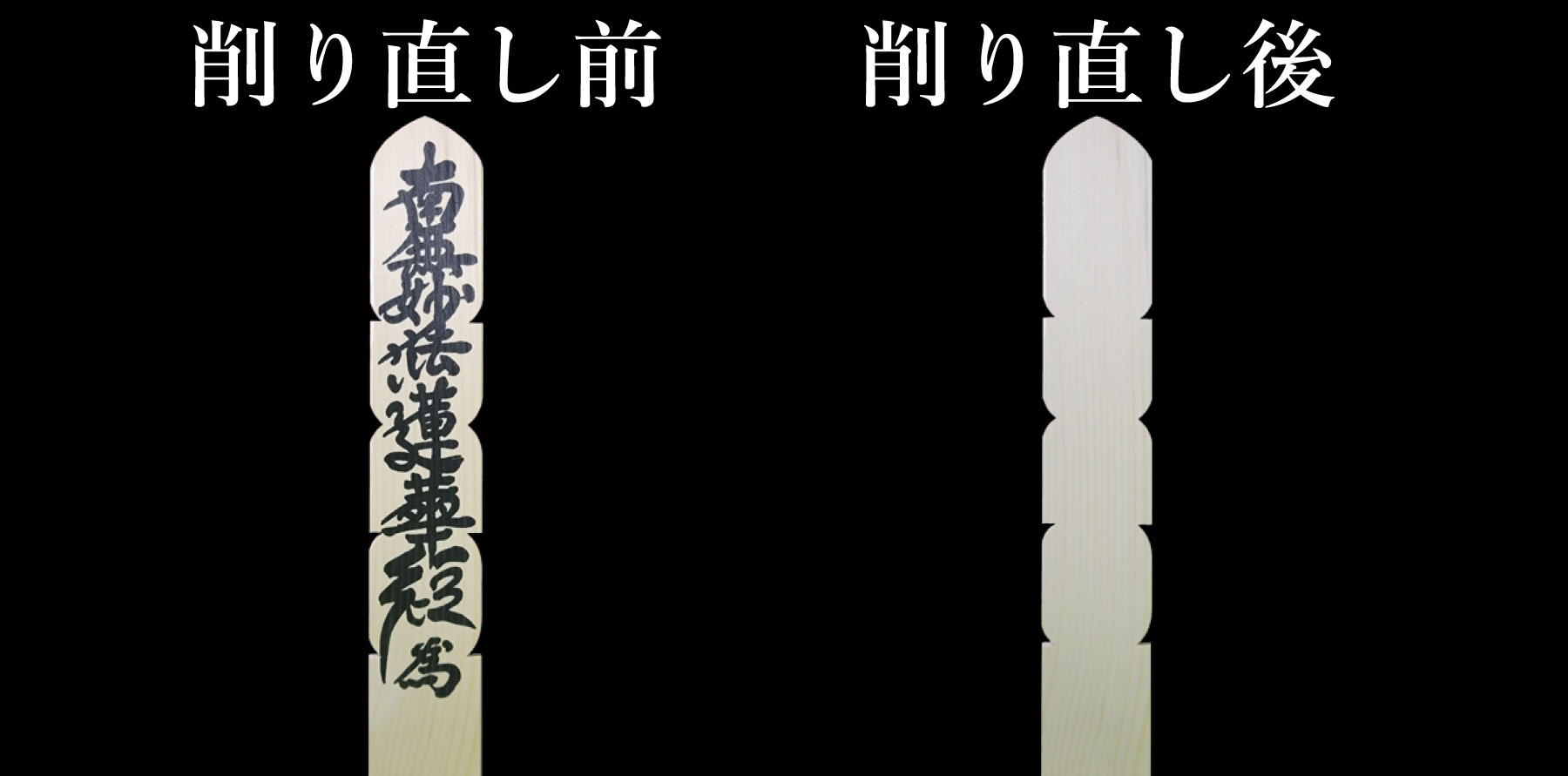






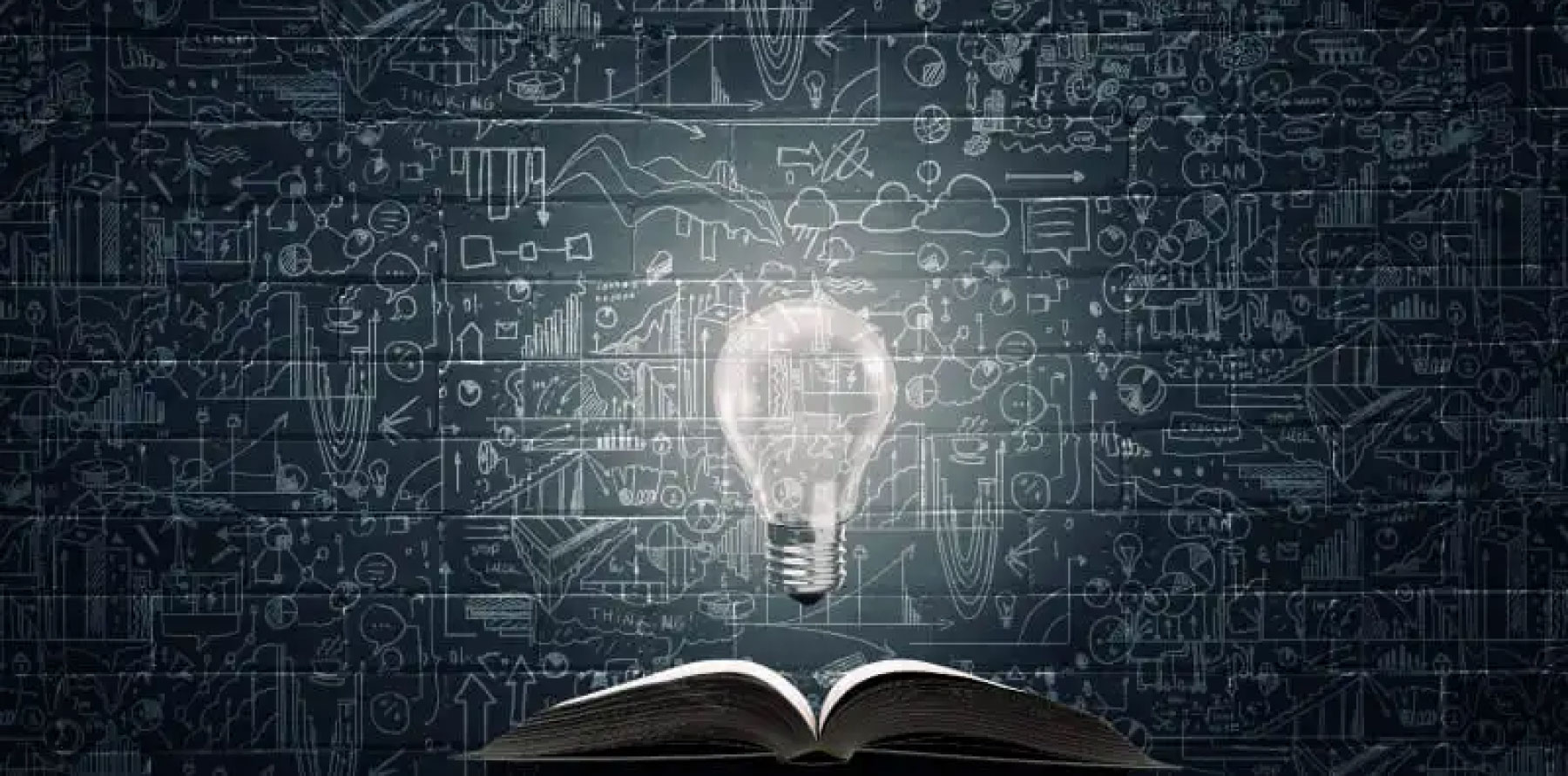

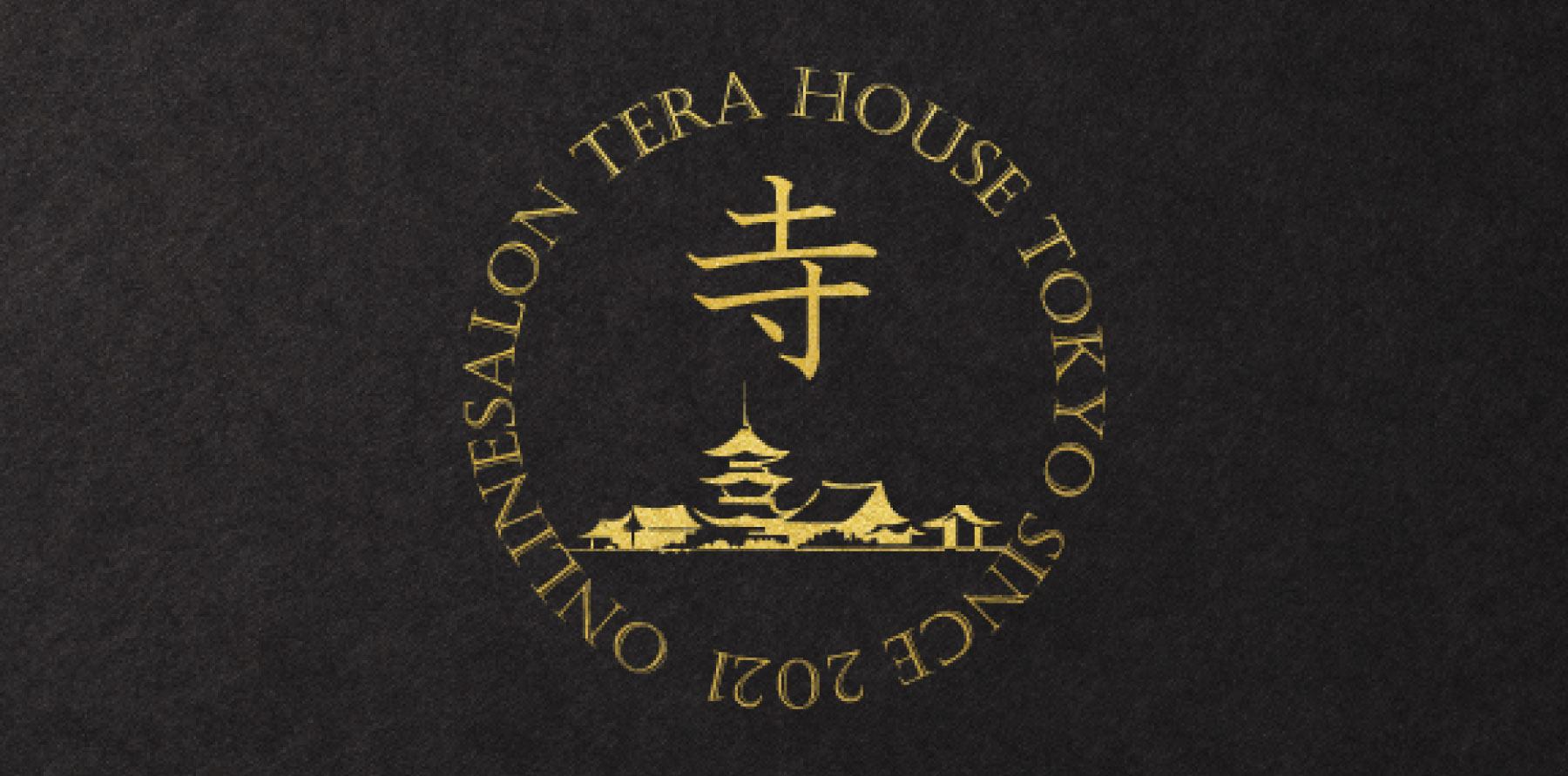
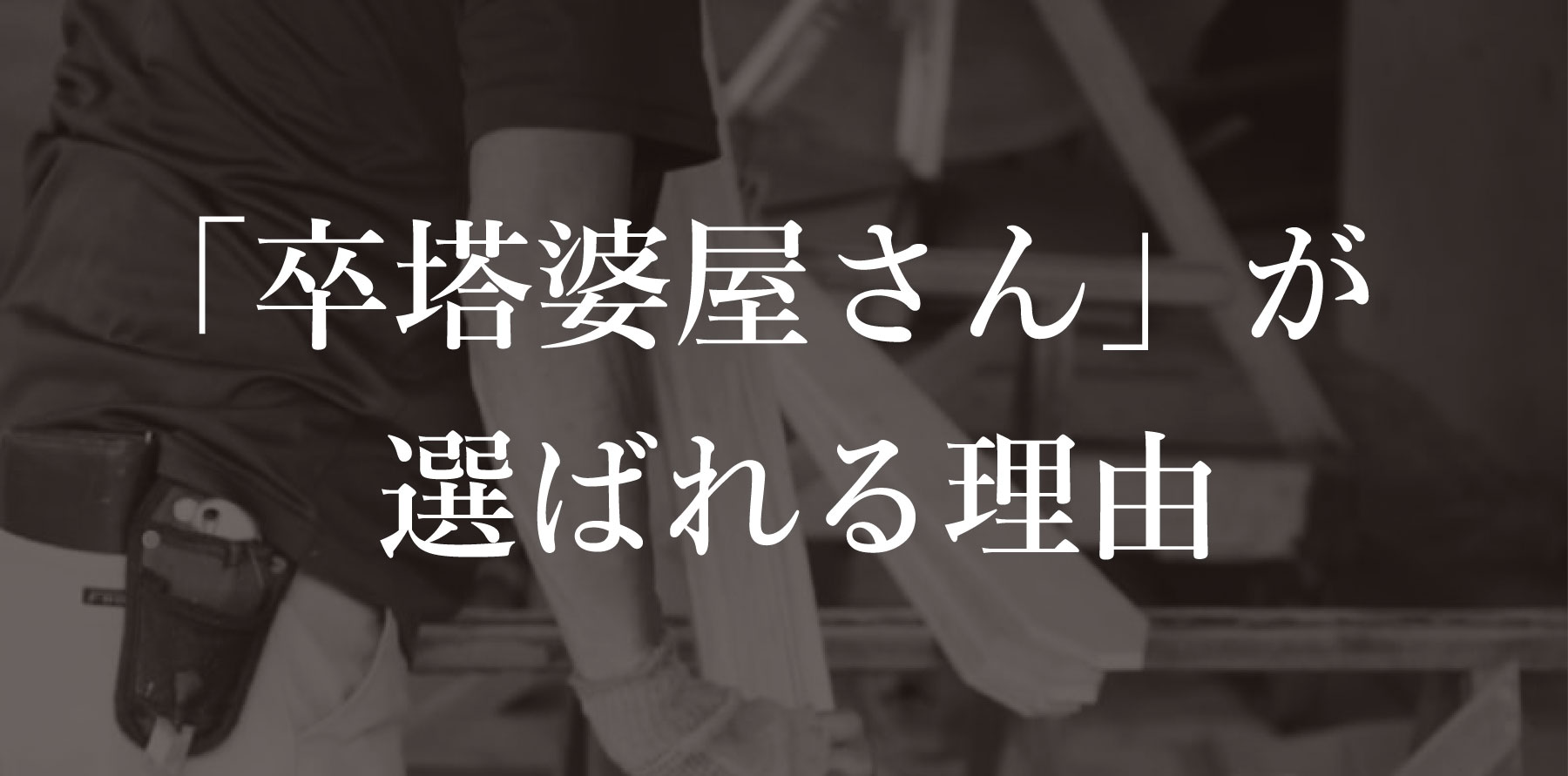
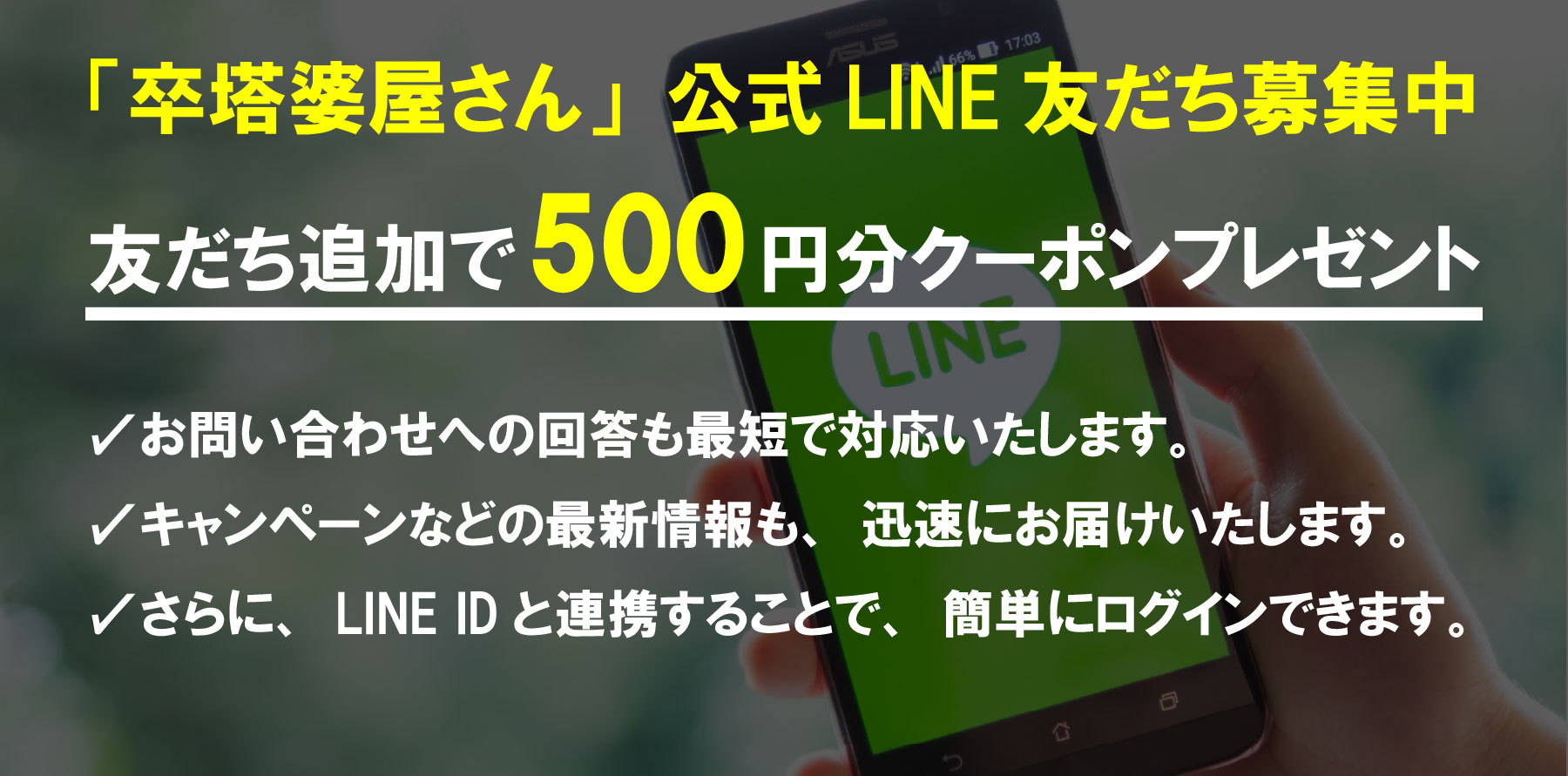


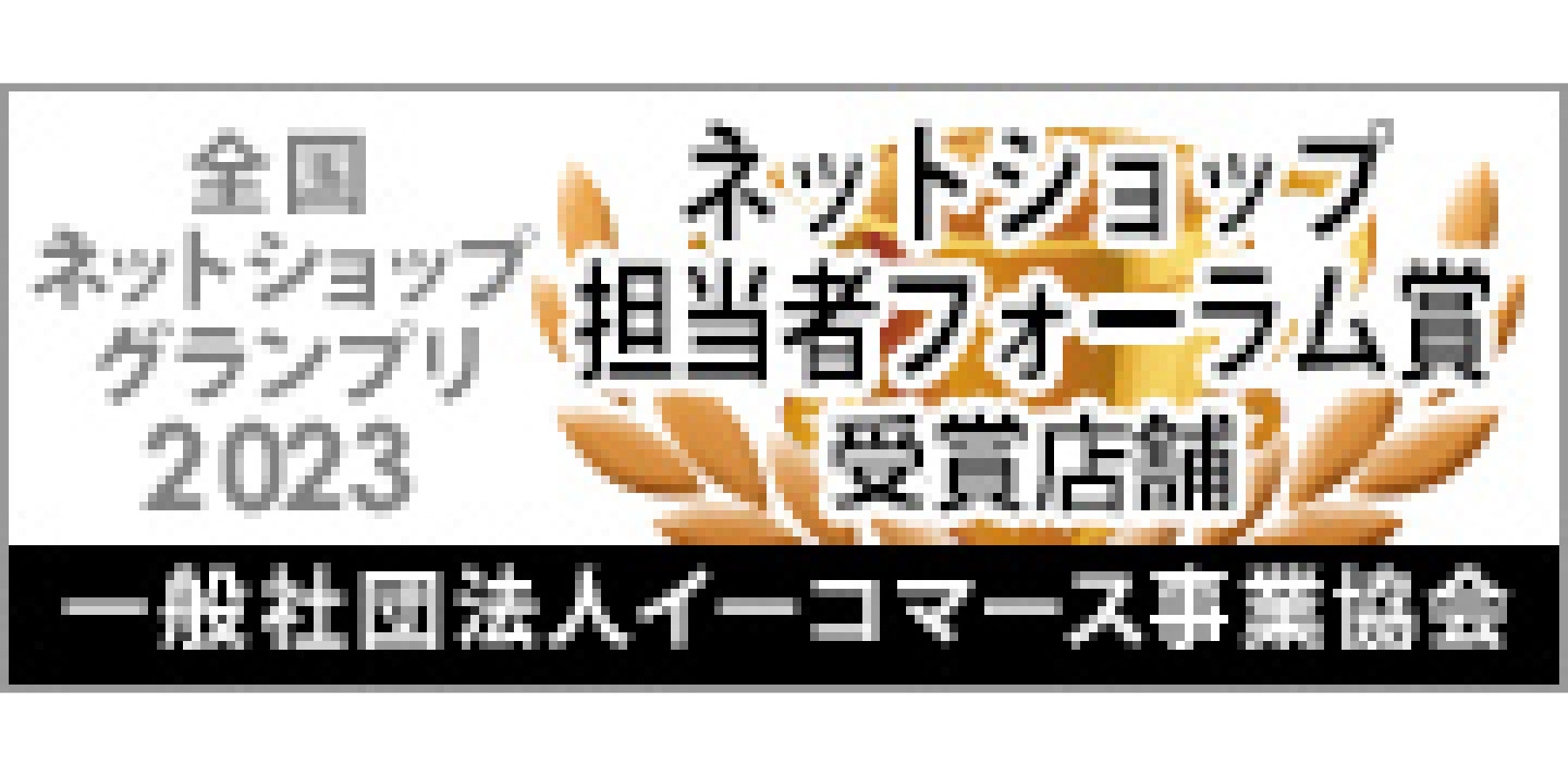




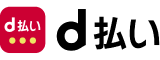





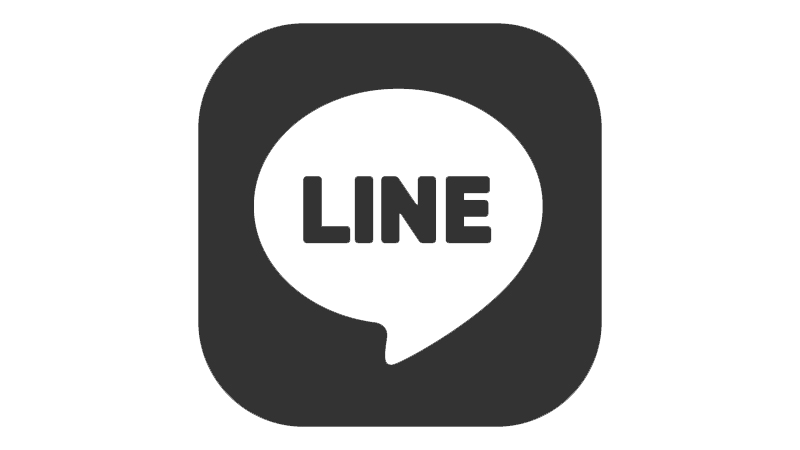
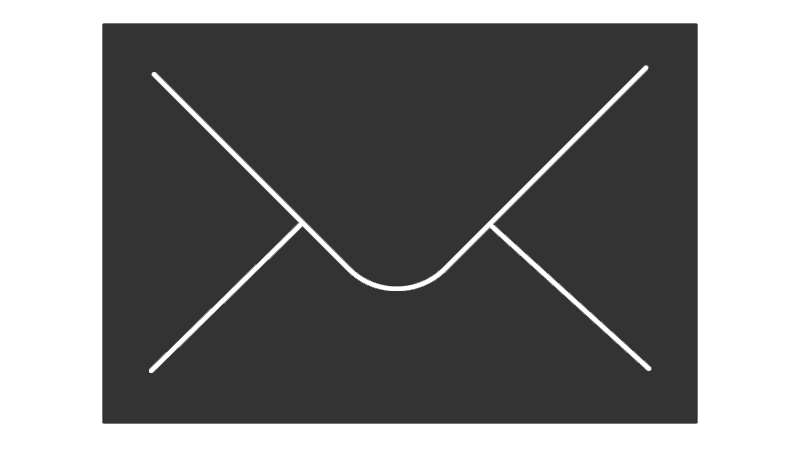

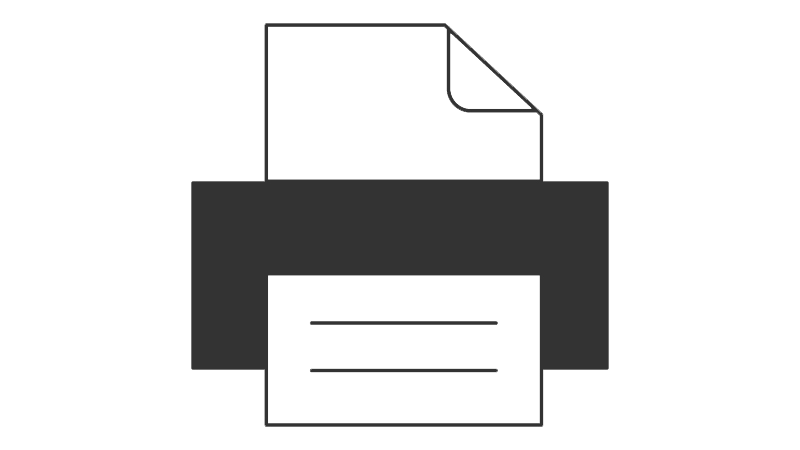
 卒塔婆(50本入)
卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)
卒塔婆(1本入)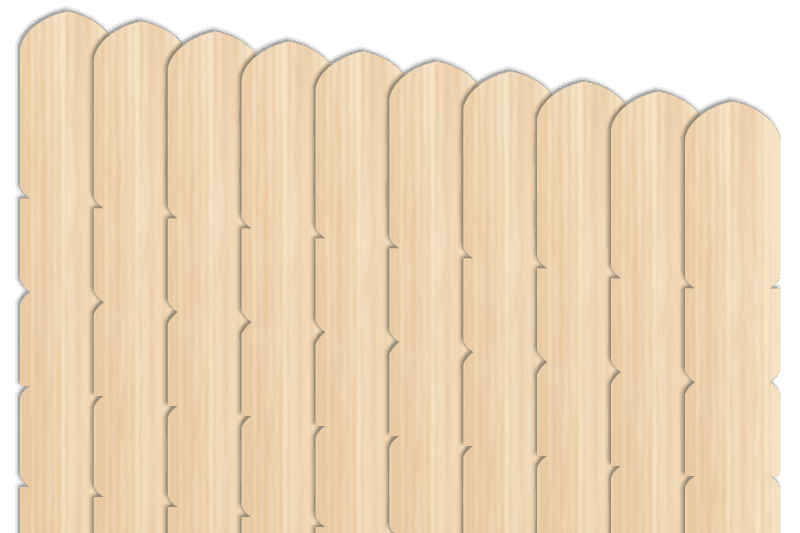 多摩産杉塔婆
多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆
ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)
神式塔婆・祭標(50本入)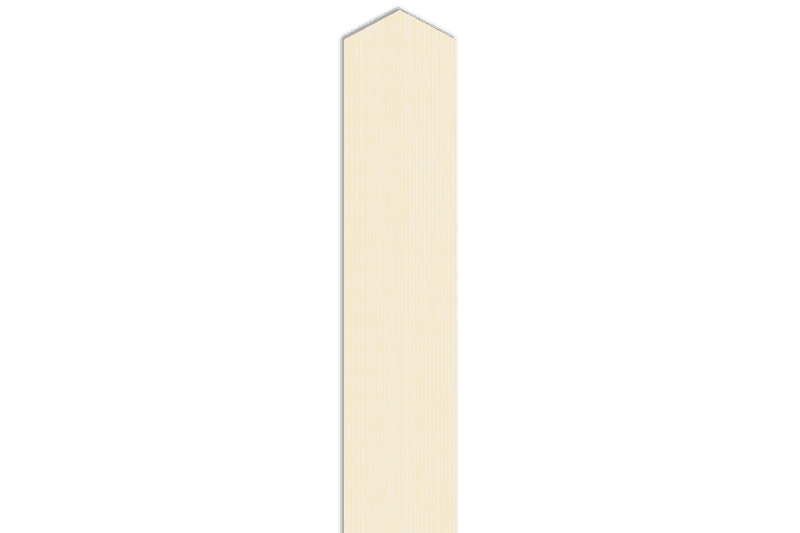 神式塔婆・祭標(1本入)
神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)
角塔婆(1本) 墓標(1本)
墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)
経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木
護摩木