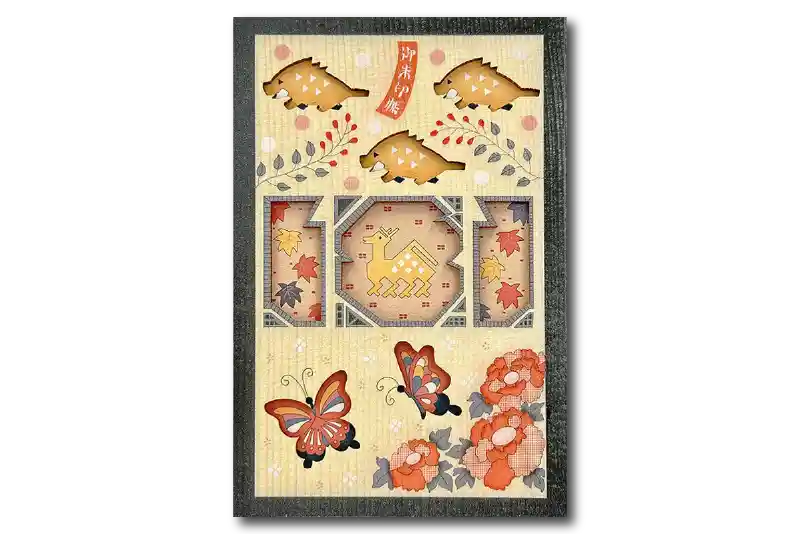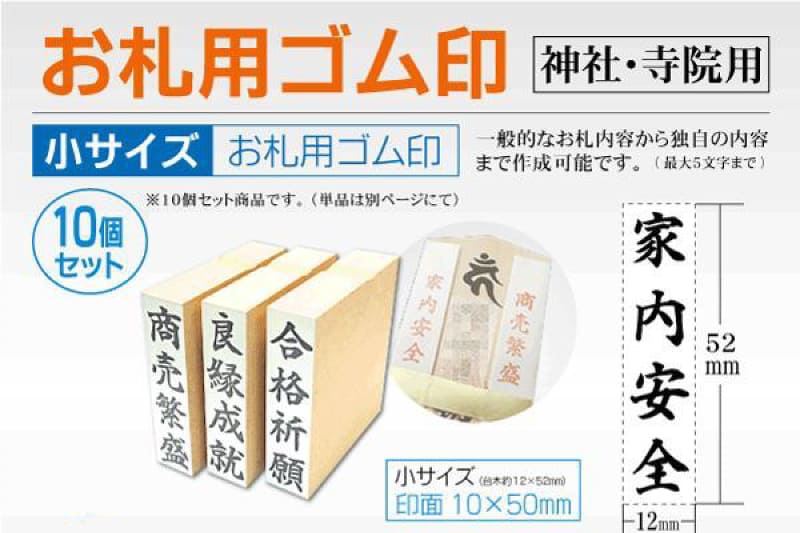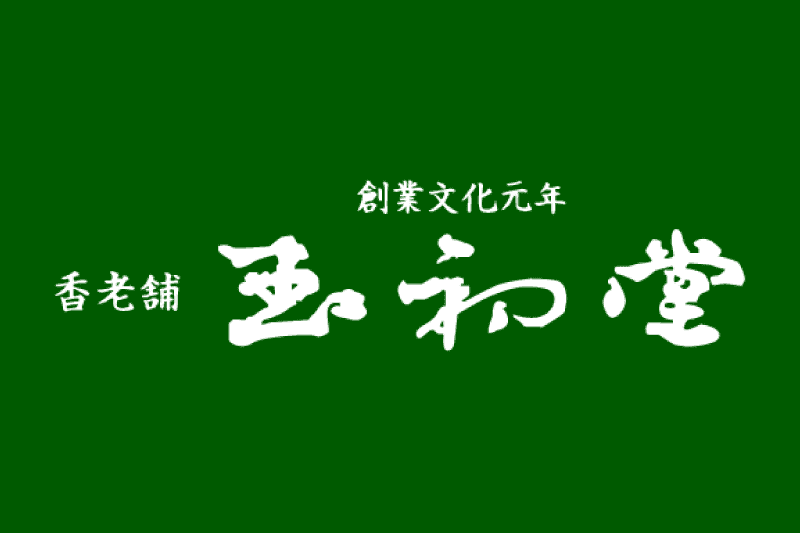花まつり(はなまつり)は、毎年4月8日に行われるお釈迦様(おしゃかさま、仏教の開祖)の誕生日を祝う仏教行事です。
日本各地の寺院でお祝いされ、正式には「灌仏会(かんぶつえ)」や「降誕会(ごうたんえ)」「仏生会(ぶっしょうえ)」「浴仏会(よくぶつえ)」「竜華会(りゅうげえ)」「花会式(はなえしき)」など、様々な呼び名があります。
この日は、**花御堂(はなみどう)**と呼ばれる小さなお堂をたくさんの花で飾り、その中に誕生仏(たんじょうぶつ)という、お釈迦様が生まれた時の姿の像を安置します。
そして参拝者は、誕生仏の頭上に甘茶(あまちゃ)と呼ばれる甘いお茶をひしゃくでそそぎかけ、お祝いします。
なお、花まつりは特定の宗派に限らず広く行われる行事で、仏教ではとても大切なお祭りです。
地域によっては旧暦の4月8日や、新暦の5月8日前後に行うところもあります。
目次
花まつりの由来と歴史
花まつりの起源は、お釈迦様が誕生した古代インドまで遡るとされています。
その後、中国では4世紀頃の後趙という時代に始まり、唐や宋の時代に盛んになりました。
日本には飛鳥時代の推古天皇の頃(606年)に伝わり、奈良県の元興寺(がんこうじ)で最初の花まつりが行われたと伝えられています。
奈良時代にはすでに大きなお寺で誕生仏を祀る行事として広まっており、その当時の誕生仏の像が現存していることも確認されています。
平安時代になると寺院の年中行事として一般化し、江戸時代には寺子屋などを通じて庶民にも広がりました。
つまり、日本では古くから宮中行事や寺院の伝統行事として受け継がれ、時代を経て多くの人々に親しまれるようになったのです。
「花まつり」という名前自体は明治時代の末頃から使われ始めたと言われます。
その理由には諸説ありますが、ちょうど4月上旬がお花が美しく咲き誇る季節であることや、お釈迦様がお生まれになったルンビニー(現在のネパール)の花園に由来するという説が有力です。
実際、行事では花で飾ったお堂を使うため、「花まつり」という呼び名は季節感とお祝いの内容にふさわしく、次第に一般にも定着しました。
また、明治時代に日本の仏教者が海外でこの誕生祭を紹介した際、「ブーレメン・フェスト(花の祭り)」という表現が新聞で「花まつり」と訳され広まったというエピソードも伝えられています。
花まつりの宗教的な意味と伝説
お釈迦様(ブッダ、釈尊)は、今から約2500年前、現在のネパール国境近くにあったルンビニーの花園で、釈迦族の王子としてお生まれになりました。
仏教の伝説によれば、お釈迦様は誕生してすぐに立ち上がり、東西南北それぞれに7歩ずつ歩んだあと、右手で天を、左手で地を指し「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげ ゆいがどくそん)」と宣言されたといいます。
この難しい四字熟語には、「この世に生を受けた一人ひとりの命は、他の誰にも代えられない尊いものだ」という意味が込められており、すべての命の尊さを示す仏教の精神を表しています。
お釈迦様ご自身の尊さだけでなく、あらゆる人々の命もかけがえのない尊厳を持つという教えと解釈できる言葉です。
伝説では、お釈迦様がお生まれになった瞬間、周囲の花々が一斉に美しく咲き乱れ、空からは甘露(かんろ)の雨が産湯のように降り注いだと伝えられます。
天上から九匹の龍が現れて香り高い甘い雨を降らせ、新生児であるお釈迦様の身体を清めたという神秘的な説話です。
この「甘露の雨」の伝説にちなみ、花まつりでは誕生仏の像に甘茶(アジサイの一種であるヤマアジサイの葉から作った甘いお茶)をそそぐ儀式が行われます。
甘茶をかける所作は、お釈迦様の誕生を祝福して天から降った甘い雨を再現するものなのです。

現代の花まつりの様子と地域差
今日でも毎年4月8日前後になると、全国各地の寺院で花まつりが開催されます。
各寺では境内に花御堂を設置し、訪れた人々がお堂の中の誕生仏に甘茶をかけてお参りします。
仏教系の幼稚園や学校でも、この時期に花まつりの行事を行うことが多く、子どもから大人まで広く親しまれています。
先述のように、多くの寺院で参拝者に甘茶が振る舞われ、自由に飲めるようになっています。
甘茶には砂糖などの甘味料は入っておらず、アマチャという植物の葉を煎じた自然の甘みのお茶です。
そのため、小さな子どもでも安心して飲むことができ、ほんのりとした甘さを楽しめます。
甘茶を自宅で淹れて楽しむ人もおり、ネット通販などで茶葉を購入することもできます。
一部の地域では古くからの風習で、旧暦4月8日(新暦では約1か月遅れ)に行う寺院もあります。
例えば、東北や北陸の一部では、桜の開花時期に合わせて5月8日に行われるケースもあるようです。
このように、地域や寺院によって開催日や細かな風習に違いはありますが、「お釈迦様の誕生日を祝う」という根本的な趣旨は共通しています。
花まつり当日は、お寺によってさまざまな工夫を凝らした催しも行われます。
多くの花をお供えしたり、境内を華やかに飾り付けたりするほか、音楽演奏や法要といったイベントを合わせて開催するところもあります。
特に**稚児行列(ちごぎょうれつ)**と呼ばれる子どもたちのパレードは、各地の花まつりでよく見られる光景です。
稚児行列では、小さな子どもたちが仏様に仕える稚児に扮し、かわいらしい装束や花の飾りを身につけて隊列を組み、街を練り歩きます。
これは、お釈迦様の誕生をお祝いすると同時に、子どもたちの無病息災と健やかな成長を願う行事でもあります。
実際、花まつりは「子どもの身体健全・所願成就」を祈るお祭りという側面もあり、多くの寺院で子どもたちが主役になる催しが用意されています。

写真は、東京・浅草の浅草寺で行われた花まつりの稚児行列の様子です。
園児たちが頭に花の冠をつけ、手をつなぎながらお釈迦様の誕生を祝うパレードを楽しそうに歩いています。
このように、花まつりはお子様からお年寄りまでみんなが参加できるお祭りであり、各寺院も工夫を凝らして誰もが楽しめる行事にしています。
また、地域によっては白象(はくぞう)の模型を子どもたちがひいて練り歩くところもあります。
これは、お釈迦様の母マーヤ夫人が白い象の夢を見てお釈迦様を身ごもったという伝承にちなみ、白象が神聖なシンボルとされているためです。
大きな白象の山車に花御堂と誕生仏を載せ、子どもたちが綱を持って引っ張りながら町を巡行する姿は、とても微笑ましく地域の風物詩にもなっています。
このように、現代の花まつりでは、伝統的な儀式とともに、子どもたちも参加できるイベント性のある催しが各地で展開されています。
子どもや一般の人へ伝える際の工夫
花まつりは、クリスマスほど一般には知られていないかもしれませんが、仏教における「お誕生日のお祝い」です。
子どもや仏教になじみのない方に説明するときは、「4月8日はお釈迦様の誕生日なんだよ」と、まずシンプルに伝えてみましょう。
それだけでも、子どもたちは「自分たちと同じように仏様にもお誕生日があるんだ」と理解しやすくなります。
また、近くのお寺で花まつりが行われる際には、ぜひ親子で参加してみるのも良いでしょう。
参拝者向けに用意されたひしゃくを使って、お釈迦様の像に甘茶をかける体験は、きっと楽しい思い出になるはずです。
実際に自分で甘茶をかけたり飲んだりすることで、子どもにとって仏教行事がより身近に感じられる貴重な体験となります。
花まつりを通して、仏様の教えだけでなく、「いのちの尊さ」や「感謝の気持ち」の大切さを、子どもたちと一緒に考えてみるのも良い工夫です。
お釈迦様の誕生にまつわるエピソード(花が咲き乱れ、甘い雨が降った話や「天上天下唯我独尊」の意味など)を、絵本や紙芝居などでわかりやすく伝えるのも効果的です。
例えば、「生まれてきた命は、それぞれかけがえのない大切なものなんだよ」といったメッセージを、子どもに噛み砕いて話すと、花まつりの宗教的な意味も自然と心に届くはずです。
「みんなが元気に大きくなりますように」と願いながら甘茶をかけたり飲んだりすることで、子どもたちも自分や周りの人の命を大事に思う気持ちを育むことができます。
おわりに
花まつりは、仏教徒だけでなく、誰にとっても心温まる行事です。
春爛漫の季節、美しい花々に囲まれてお釈迦様の誕生をお祝いする時間は、私たちに命の尊さや日々の感謝を改めて感じさせてくれます。
もしお近くのお寺で花まつりが催されるようでしたら、ぜひご家族やお友達と足を運んでみてください。
甘茶の優しい甘みとともに、ほっと和やかな気持ちになれることでしょう。
また、お釈迦様のお誕生日を祝うこの伝統行事を通じて、仏教の教えや日本の文化に触れる良い機会にもなるはずです。
【参照元一覧】
東京新聞「浅草寺で行われた花まつりの様子」
浄土宗公式サイト – https://www.jodo.or.jp
曹洞宗公式サイト – https://www.sotozen-net.or.jp
浄土真宗本願寺派公式サイト – https://www.hongwanji.or.jp
日蓮宗公式サイト – https://www.nichiren.or.jp
日本仏教伝道協会「花まつりについて」 – https://www.bdk.or.jp
京都・高台寺公式サイト(花まつりの取り組み紹介) – https://www.kodaiji.com
曹洞宗総合研究センター「仏教行事に関する研究」
文化庁「宗教年鑑」 – https://www.bunka.go.jp
宗教新聞「花まつりの歴史と現代の意義」
この記事を書いた人
DAISUKE YAJI
プロフィール
1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業
1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社
2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社
2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社
2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任
2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)
2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞
2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞
2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞
義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯
趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

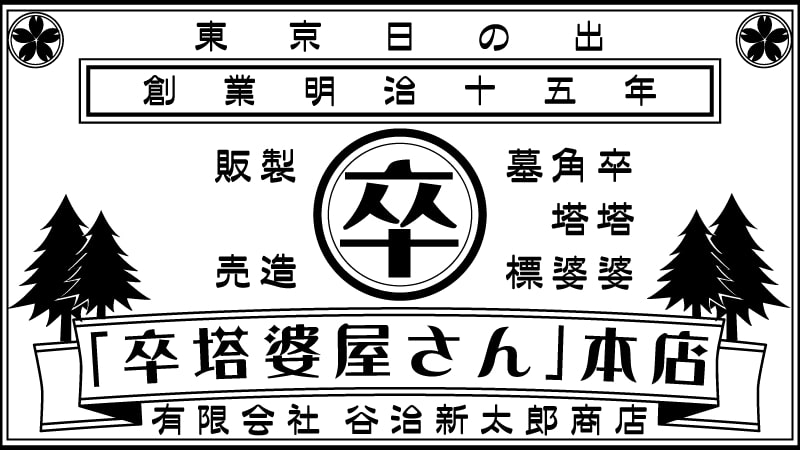








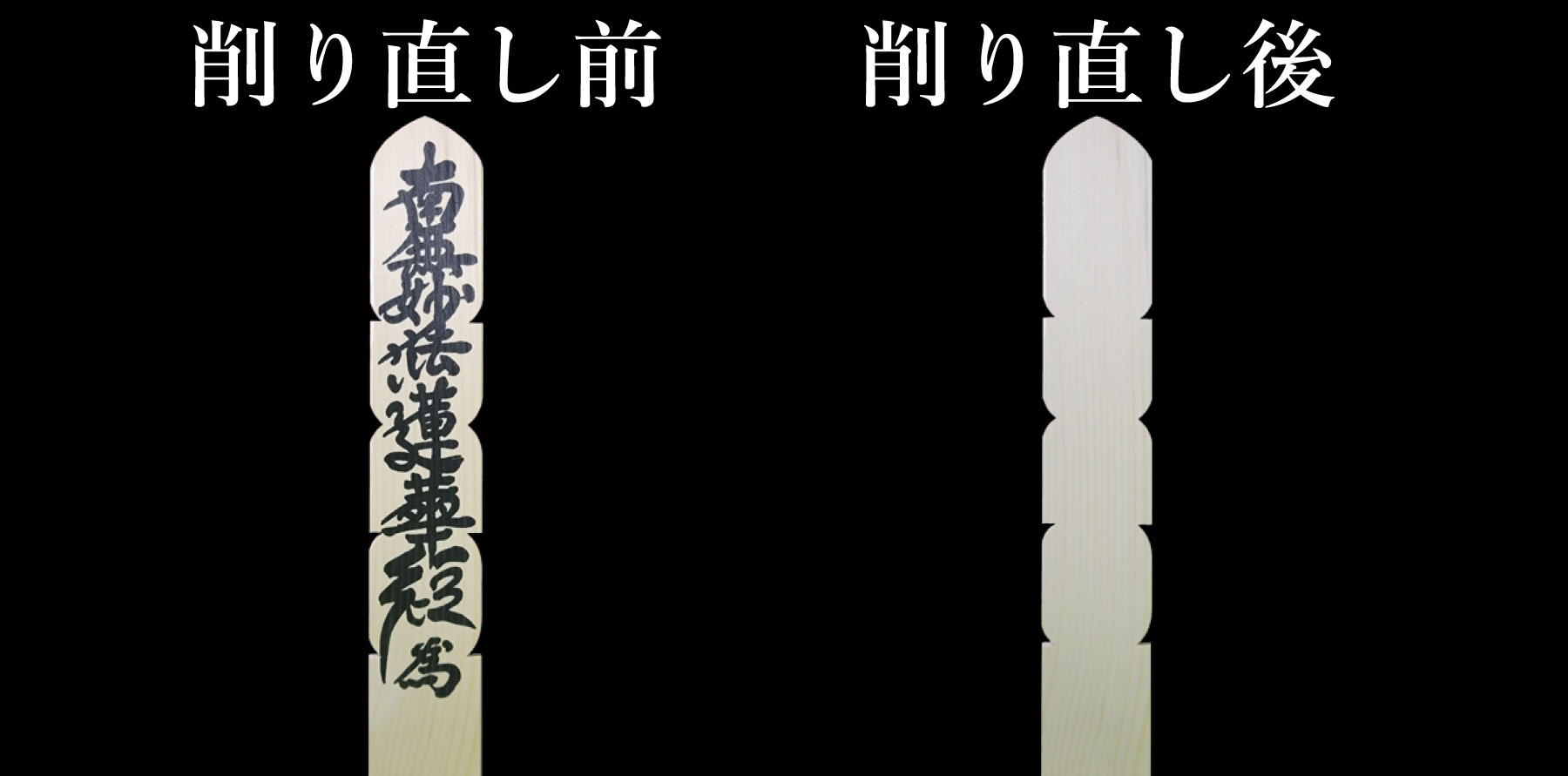






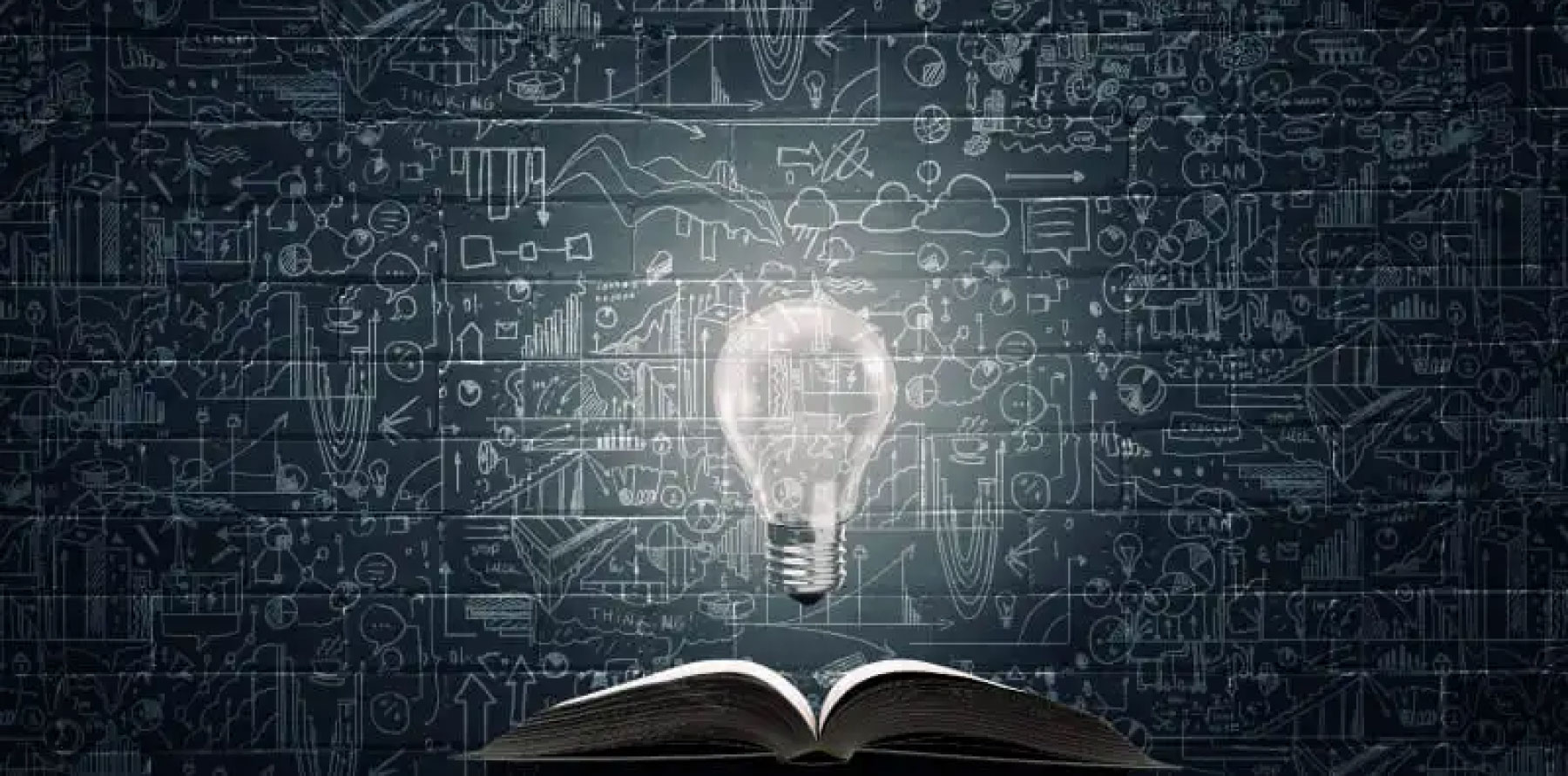

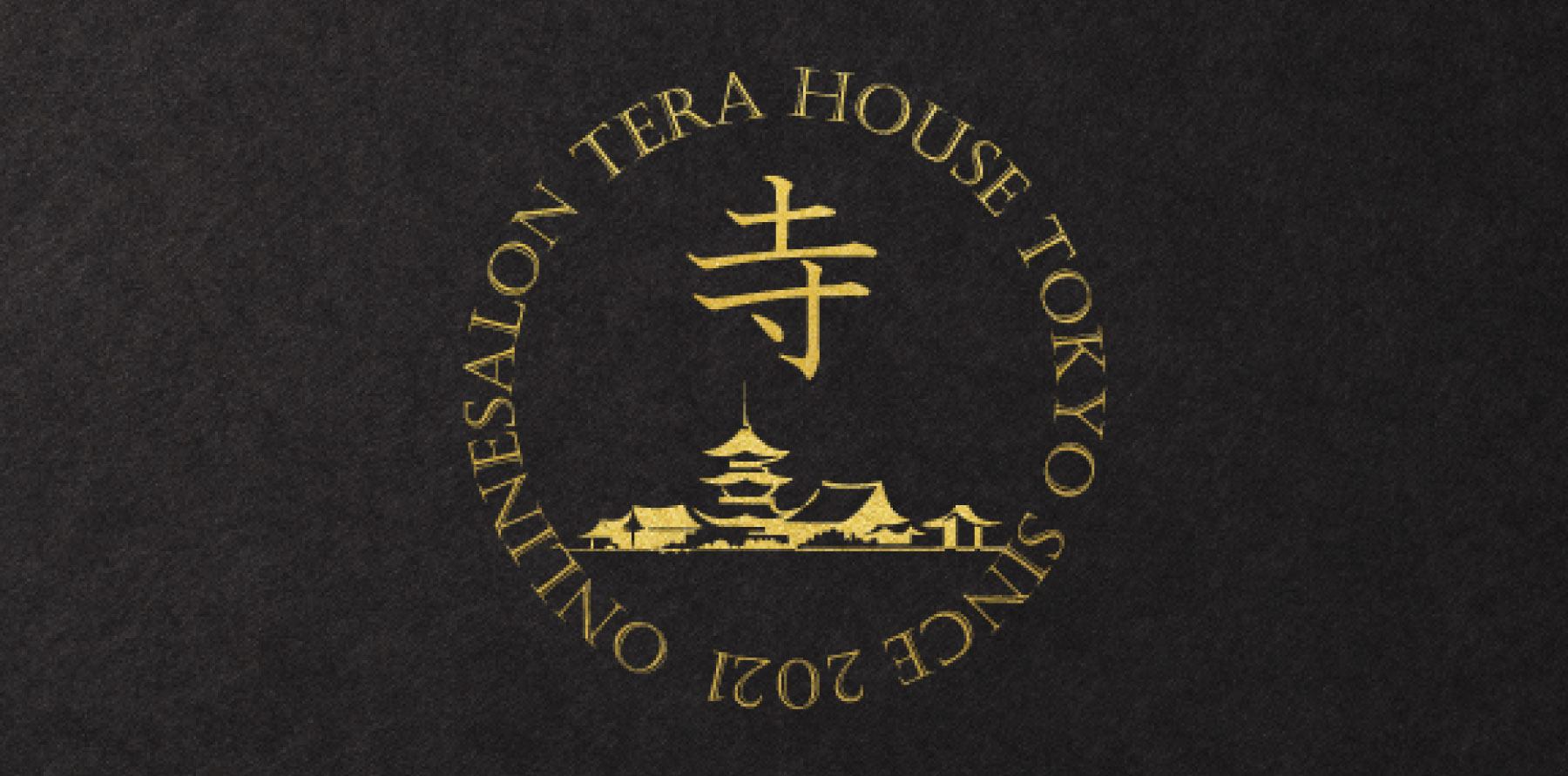
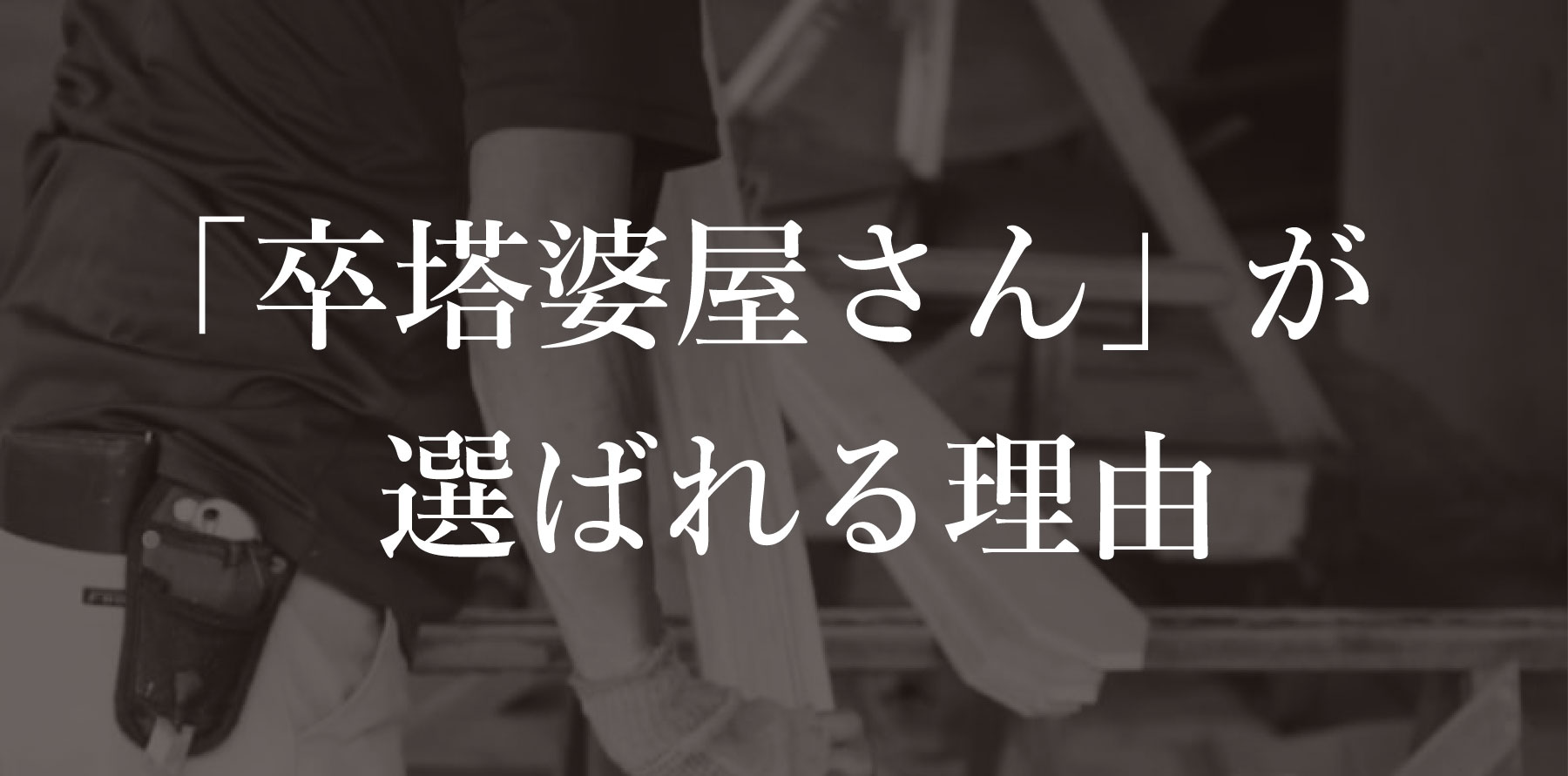
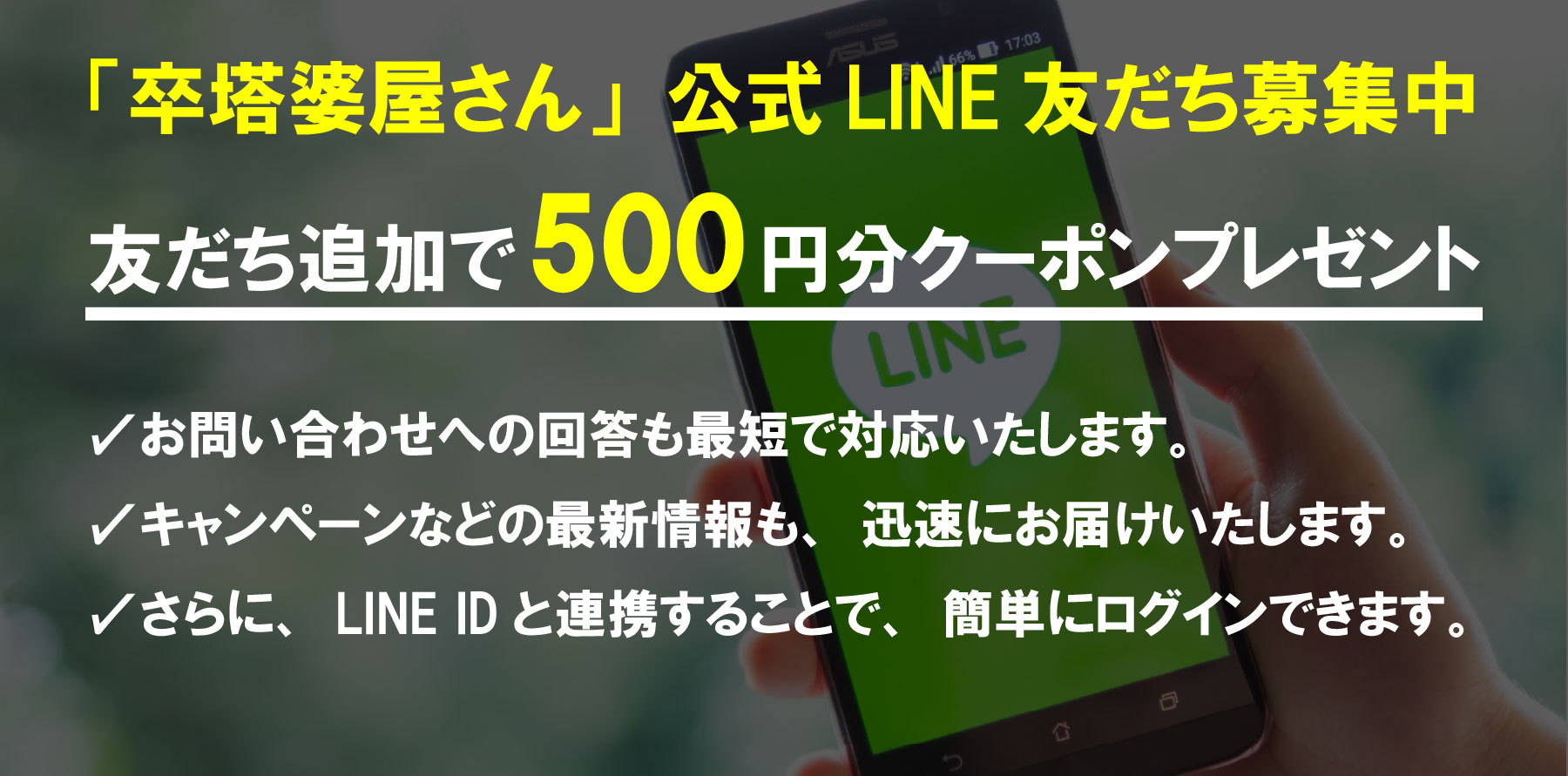


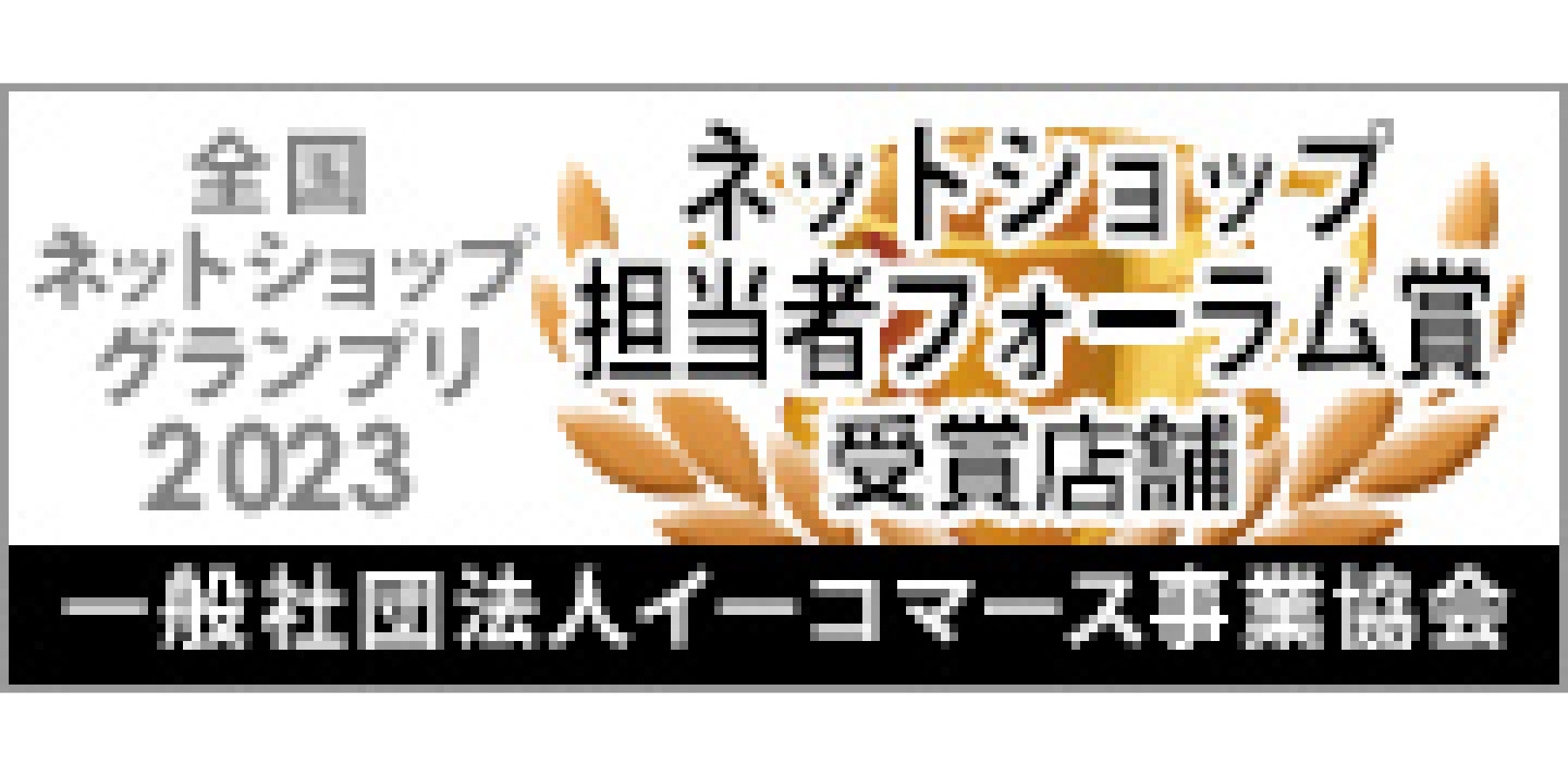




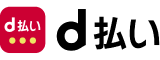





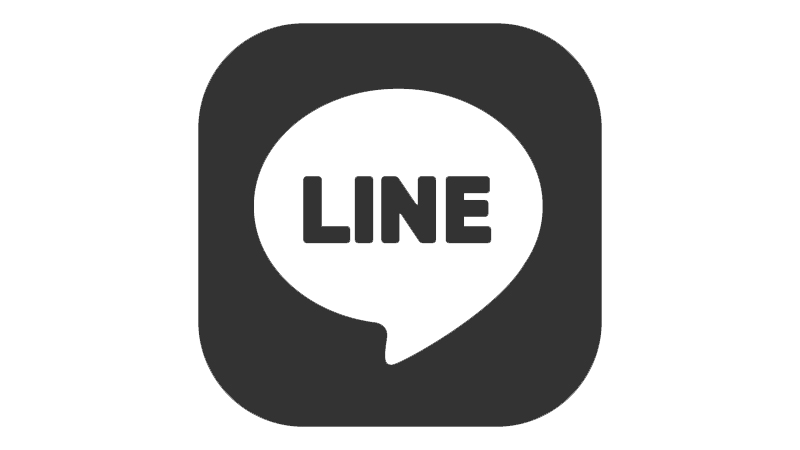
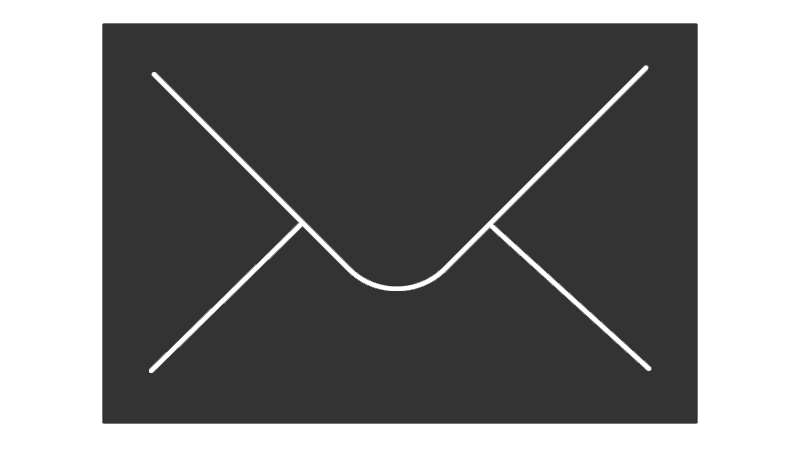

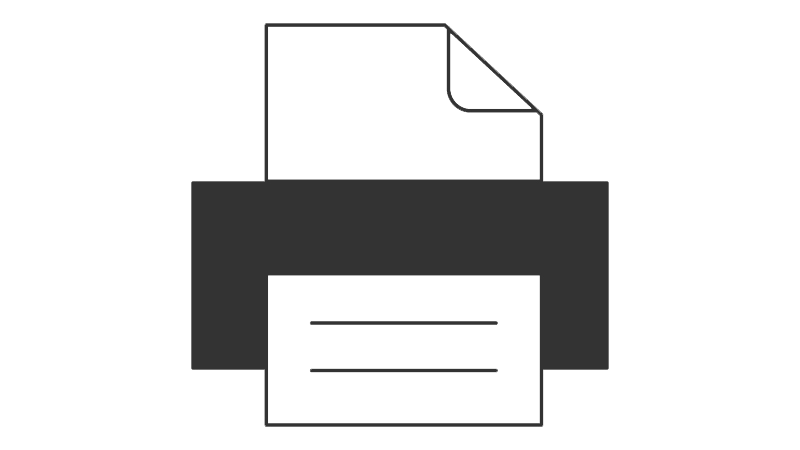
 卒塔婆(50本入)
卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)
卒塔婆(1本入)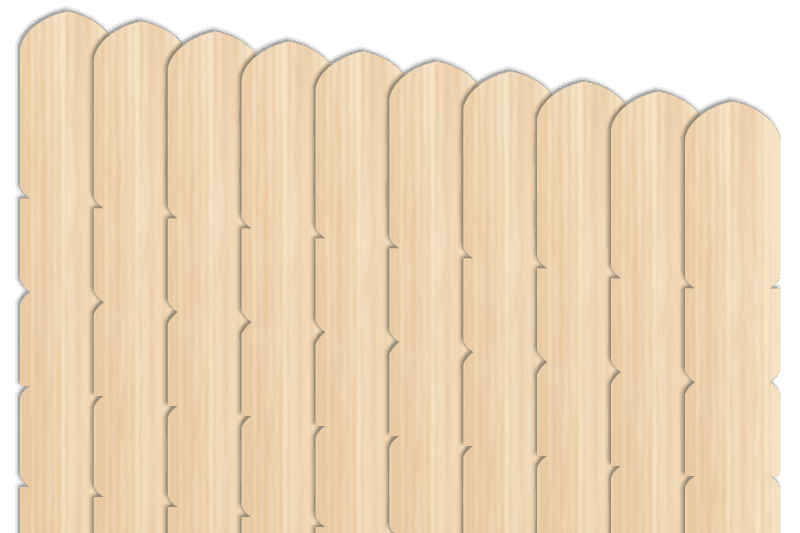 多摩産杉塔婆
多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆
ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)
神式塔婆・祭標(50本入)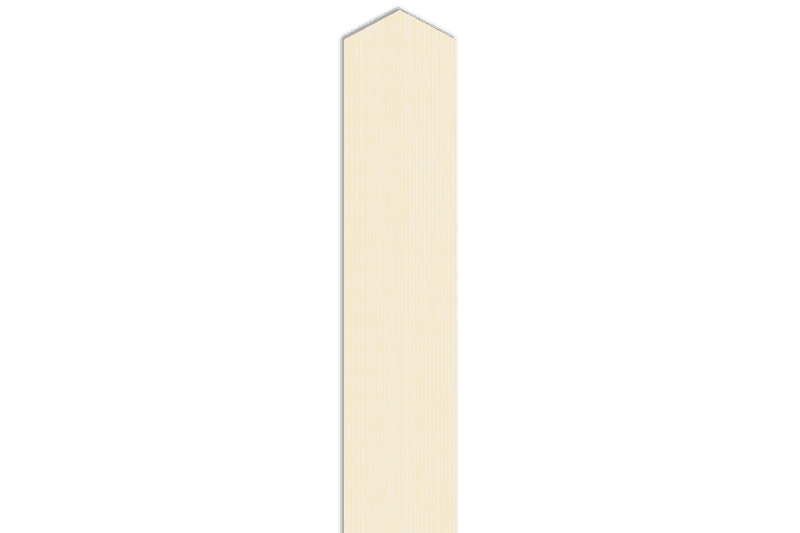 神式塔婆・祭標(1本入)
神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)
角塔婆(1本) 墓標(1本)
墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)
経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木
護摩木