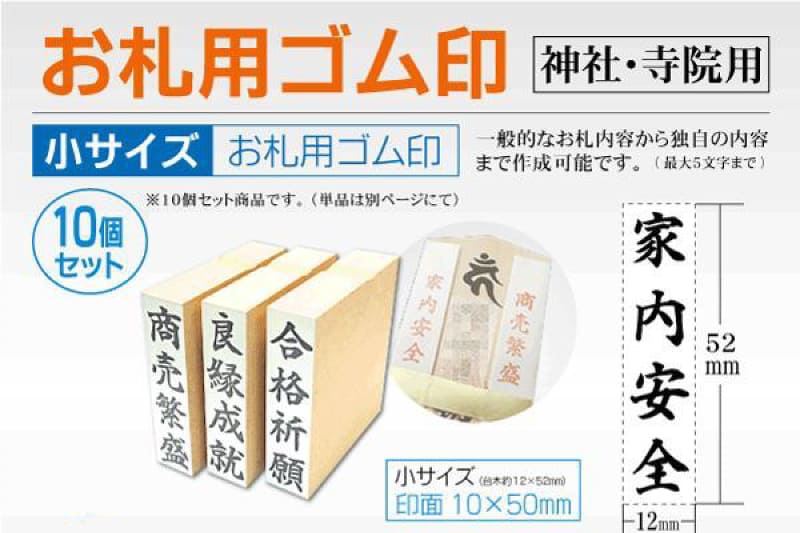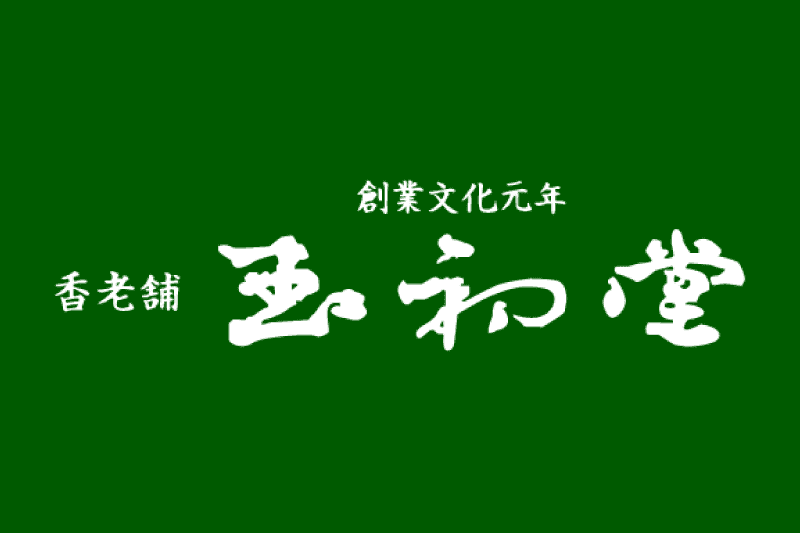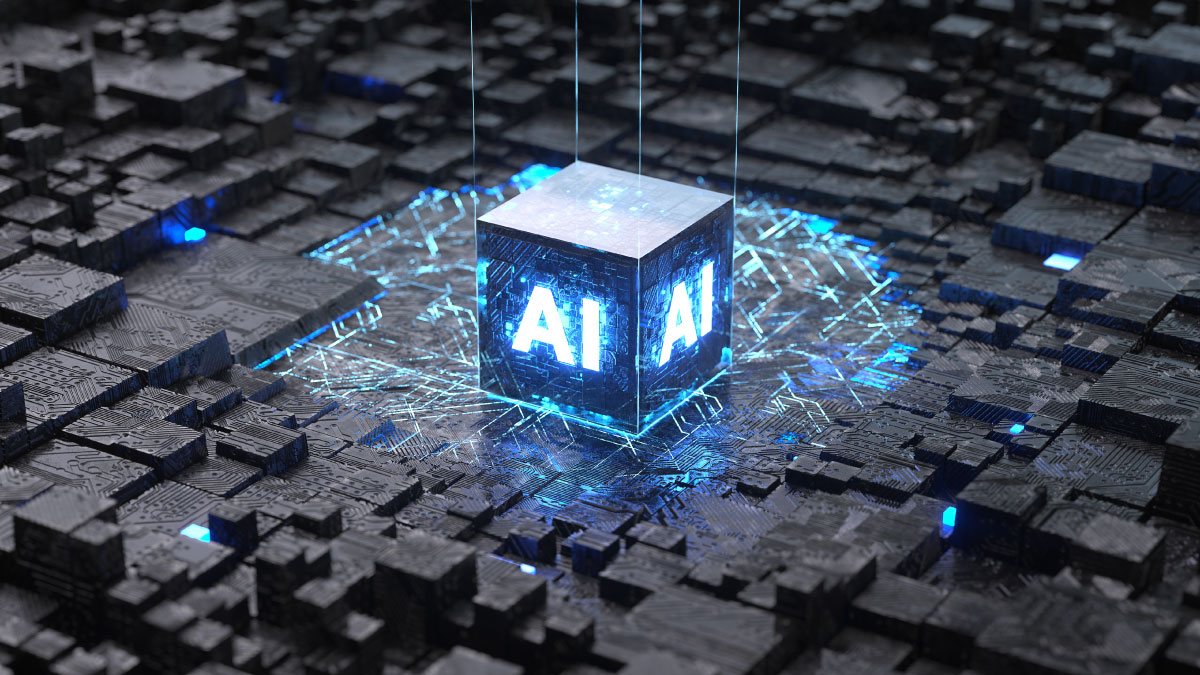
現代の寺院では、 人工知能(AI) を活用した新たな取り組みが国内外で増えつつあります。たとえば京都・高台寺では、人型ロボットの観音菩薩「マインダー」が法話を行い、従来仏教に関心の薄かった層にも教えを届けようとしています。中国・北京の龍泉寺でも、愛らしい**ロボット僧侶「賢二(シエル)」**が読経や来訪者の質問に答える試みが行われています。こうした例は一見ユニークですが、寺院でのAI活用は決して特別な話ではなく、檀家管理から法要支援まで幅広い分野で実用化が進んでいます。本記事では、寺院におけるAI活用事例とその可能性・課題について、最新動向を踏まえて分かりやすく紹介します。
目次
AI活用が期待される主な分野と実例
寺院運営においてAIが役立つ場面は多岐にわたります。以下では、特に注目される活用分野ごとに具体的な実例を見てみましょう。
1. 檀家管理・寄付対応の効率化
多くの寺院では檀家(門信徒)台帳の管理や行事の案内、会計処理など事務作業に多くの時間を割いています。AIによるデータ分析や自動化を導入することで、これらバックヤード業務の効率化が期待できます。実際、来訪者や檀家の年齢層・参拝回数などのデータを統計分析し、行事案内や経営改善に活かす取り組みも登場しています。例えば、檀家の命日・回忌法要の情報をAIが自動リマインドしたり、寄付金の入金状況を分析して将来の収支を予測するようなシステムです。また、電話音声AIによる高齢檀家の見守りサービス「おてらコール」の実証実験も開始されました。このサービスでは住職の肉声メッセージを自動発信し、高齢の一人暮らし檀家の安否確認と相談受付を行います。異常時には家族や福祉機関と連携できる仕組みで、地域コミュニティに密着した寺院ならではの福祉サービスとして注目されています。さらに、寄付行動とAIに関する興味深い研究もあります。京都の高台寺で、ロボット僧侶(マインダー)と人間の僧侶それぞれの説法を聞いた人では、後者の方が寄付額が多かったとの実験報告もあり、信徒の信頼感という観点からAI活用の課題を浮き彫りにしています。
2. 広報・参拝者案内への活用
寺院の広報活動や参拝者対応にもAIが力を発揮しています。チャットボットによる問い合わせ対応はその一例です。長野県の善立寺では、IBMのWatsonを使ったチャットボットを公式サイトに設置し、寺の見どころ、アクセス方法、駐車場の有無など、参拝者から寄せられやすい質問に24時間自動応答する試みを行いました。このチャットボットは多言語対応も可能で、海外からの訪問者にも即時に情報提供できる利点があります。運用の中で蓄積されたログを分析することで、「お布施はいくら包めば良いか」や「仏教とキリスト教はどちらが良いのか」といった、人々が僧侶には聞きにくかった本音の質問が多く寄せられることも分かりました。現在この試みは一旦休止していますが、今後より高度なAIを導入すれば、人手をかけずに参拝者の疑問解消やニーズ把握ができると期待されています。
また、SNS発信の自動化も広報分野の注目活用例です。ChatGPTのような生成AIを使えば、行事案内文や法話エッセイの草稿を作成し、住職が手直しして発信するといった効率化が可能です 。実際に寺報(寺のニュースレター)記事の下書きをAIに生成させ、アイデア出しに活用しているお寺もあります。さらに、コロナ禍以降にはバーチャル参拝やオンライン法要も普及しましたが、AI技術を用いて寺院や文化財を3Dスキャンしバーチャル空間で案内する試みも進んでいます 。例えば、自宅にいながらリアルタイムで御堂内部を巡り解説を聞けるサービスや、VRゴーグルを通じて臨場感ある参拝体験ができるコンテンツなど、広報・布教の手段としての可能性が広がっています。
3. 法要支援(儀式へのAI活用)
読経や法要といった宗教儀式の分野でもAIの活用事例があります。特に話題となったのが、人型ロボットによる読経代行です。ソフトバンク社のロボット「Pepper(ペッパー)」は、2017年の東京国際葬祭展示会で僧侶姿のロボット法要を実演し注目を集めました。ペッパーに経文唱和ソフトを搭載し、木魚を叩きながらお経を上げるこのロボット僧侶は、人手不足時の代役となり得るだけでなく、葬儀一件あたり5万円程度と人間の僧侶を呼ぶより費用を大幅に抑えられるメリットが紹介されました。実際の葬儀現場で導入された例はまだ少ないものの、過疎地や後継者不在のお寺では「いざという時の選択肢」として検討する動きもあります。また、法要の準備や進行管理にもAIが役立ちます。過去帳や年回表をAIが解析して法事の予定表を自動作成したり、遠隔地の檀家向けに法要をライブ配信する際、AIカメラが祭壇の適切な位置を判断して撮影・配信するなど、細かなサポートが可能です。将来的にはARグラスをかけた僧侶が、視界に経文や次第を表示させながら法要を執り行う、といった光景も現実になるかもしれません。
4. 説法・法話の自動生成
説法(法話)の領域でもAI活用の可能性が模索されています。京都・高台寺のロボット観音「マインダー」は、事前にプログラムされた音声合成システムを用いて約25分間にわたり般若心経の教えを講義します。その語りは標準的な内容ながら、ロボットが身振り手振りを交えて語る様子に「斬新で興味を惹かれる」という来訪者の声もあります。一方で、「ロボットの説教では心に響かないのでは?」という疑問もあります。この点については、米シカゴ大学の研究チームが行った実験が興味深い結果を示しています。ロボット僧侶の説法を聞いた人は人間の僧侶に比べて説法への信頼度が低く、寄付額も少なかったのです。研究者は「AIには真の信仰心がないため、宗教において人間の指導者を技術に置き換えると信徒の信頼を損ねる可能性がある」と指摘しています。この結果は、AIがどれほど便利になっても**「魂に響く説法」は人間にしか成し得ない部分がある**ことを示唆しています。
とはいえ、AIはあくまで僧侶を補佐するツールとして有用です。実際に、ある住職はChatGPTに「法話の原稿」を書かせ、その内容を寺報で紹介しました。出来上がった文章は一見すると違和感のない説法で、「誰が語るかによって言葉の重みが変わる」という問いを読者に投げかけています 。このようにAI生成の説法を叩き台に、僧侶が肉付けしていくことで発想を広げたり、文章作成の負担を減らすことも可能です。また、京都大学では仏典と生成AIを組み合わせたチャットボット「ブッダボット・プラス」の研究が進められています。ユーザーの悩みに対し、原始仏典(スッタニパータ)から該当箇所を引用し、その解説文を提示する仕組みで、テクノロジーでブッダの言葉を現代に蘇らせる試みとして期待されています。
5. 僧侶の教育・研修支援
AIは寺院利用者だけでなく、僧侶自身の学びや業務改善にも役立っています。たとえば福岡県の信行寺では、住職が日々ChatGPTを「仕事の相談相手」として活用しているそうです。具体的には「これからのお寺の在り方についてこう思うがどうだろう?」といったテーマで対話し、自身の考えを客観視したり、新たな着想を得るのに役立てているとのこと。対話AI相手に業務アイデアをブレストすることで、「思いもよらない気づきが得られる」といった効果を感じているといいます。このようにAIを仮想アシスタントやコーチとして位置づけ、僧侶の自己研鑽や意思決定に活かす事例も出始めました。
また、伝統的な読経や作法の習得にもAIが寄与し得ます。音声認識技術を使ってお経の音程やリズムを解析し、誤りをフィードバックするシステムがあれば、新人僧侶の習熟をサポートできるでしょう 。瞑想指導では、スマートデバイスで心拍数や脳波をモニタリングし、AIがリアルタイムにリラックス度を評価して適切なガイダンスを提供するアプリの開発も考えられます。さらに遠隔地の僧侶同士がVR空間で仮想道場を共有し、AI仏師が指南してくれる――そんな未来の研修風景も、技術的には夢ではありません。
技術導入の課題と倫理的配慮
このように多彩なメリットが語られる寺院AI活用ですが、導入にあたっては乗り越えるべき課題も存在します。まず費用面です。寺院の多くは小規模経営で財政的余裕が大きくないため、最新IT導入にはコストの壁があります。実際、全国に約8万ヶ寺ある寺院の多くは家族経営に近い体制で、IT予算も限られます。元エンジニア僧侶の古寺氏も「一番の問題は資本力」と指摘しており、たとえば業務管理クラウドを導入しようにも最低ユーザー数の制約で割高になるなど、小規模ゆえの非効率が課題となっています。費用対効果が見込めるかどうかは常に検討が必要であり、投資に見合う効果が得られる分野を見極めて優先導入する姿勢が求められます。
次に人的リテラシーの問題です。ITスキルは僧侶によって大きな差があり、高齢の住職ほどデジタルに不慣れなケースもあります。現状では「いまだにFAXが主力」というお寺も多く、せっかくAIを導入しても使いこなせなければ宝の持ち腐れです。現場の僧侶や職員が使いやすいインターフェースであること、安定して再現性高く動作することが重要で、ベンダー側のサポート体制も含め慎重な選定が必要でしょう。
データ管理やプライバシーへの配慮も欠かせません。檀家名簿や相談内容といった機微情報をAIが扱う場合、情報漏えいや不適切利用を防ぐセキュリティ対策が求められます。また、外部クラウドAIを使う際はデータの扱いについて利用規約を確認し、必要に応じて匿名化やオプトアウトの措置を講じるべきです。
さらに見逃せないのが寺院のイメージや宗教的許容度の問題です。テクノロジーの導入が伝統や権威と相容れないと捉えられると、信徒の反発や信頼低下を招く恐れがあります。実際、先述の研究が示すように「ロボット法話では有り難みが減る」と感じる人も少なくありません 。そのため、「お寺のイメージと合うか。プラスになるか」という観点で導入を判断することが大切だと指摘されています。たとえば本堂に最新機器を設置することで荘厳さが損なわれないか、AIが応対することで「冷たい印象」を与えないか、といった点は慎重に検討する必要があります。技術を前面に出しすぎず、あくまで黒子に徹させる工夫(デザインや話し方など)も求められるでしょう。
最後に倫理的な問題です。AIが人々の悩みに答える場合、その内容の正確さや妥当性に責任を持てるかという課題があります。誤った回答や偏った判断が信徒をミスリードすれば、宗教者としての社会的責任が問われかねません。ゆえに、AIが出した回答を僧侶がチェックする仕組みや、深刻な相談は自動で人間にエスカレーションする設定など、人間の関与を適切に残すことが重要です。また、AIが高度化する将来には、AI自体に倫理観や宗教的価値観をどの程度組み込むかという難題も浮上するでしょう。「AIに**どんなバイアス(価値観)**を持たせるかが重要になる」という指摘もあり、宗教的寛容さや慈悲の心といった要素をAIに学習させる試みも考えられています。
寺院活動にもたらす変化と今後の展望
AI活用は寺院の役割や活動にも少なからぬ変化をもたらします。まず、地域コミュニティとのつながり方が変わり得ます。前述の「おてらコール」のように、寺院がテクノロジーを介して檀家や地域住民の生活を見守る存在となれば、お寺は従来以上に地域のセーフティネットとして機能するでしょう。過疎化や高齢化が進む中で、「困ったときに頼れるお寺」という従来の姿をAIで拡張し、より多くの人に安心を提供できる可能性があります。
また、若年層へのアプローチ強化も期待できます。デジタルネイティブ世代にとって、AIロボットやオンライン相談は抵抗感が少なく、むしろ興味を引かれるポイントです。実際、京都のロボット観音に対して「面白い」「未来的だ」と若者が関心を示した例もあります。SNSやYouTubeでの情報発信にAIを活用すれば、ゲーム感覚で仏教の教えに触れるコンテンツを提供することも可能でしょう。たとえば仏教Q&Aクイズをチャットボットと楽しんだり、仏教の知恵を引用するAI占いのような形で日常の悩みにアドバイスするサービスなど、遊び心を交えた布教も考えられます。これらは若い世代にお寺を身近に感じてもらうきっかけとなり、将来的な信仰継承にもつながるかもしれません。
寺院内部の働き方も変わっていきます。単純作業の負担がAIで減れば、僧侶はより**「人にしかできないこと」**──たとえば傾聴やカウンセリング、教化活動や社会奉仕──に時間を充てられるようになります。現代の住職の悩みである「事務や雑務に追われて本来の布教に十分時間を割けない」という状況が改善されれば、結果的に寺院の社会的存在感は高まるでしょう。実際、IT活用に積極的な僧侶は「デジタルで効率化し、本来やるべき仏教を伝えることに集中したい」と述べています。AIはその強力な助っ人となり得るのです。
おわりに:AI時代の寺院が目指すもの
寺院でのAI活用はまだ始まったばかりですが、その潮流は今後ますます加速していくでしょう。日本全体が人口減少・少子高齢化という 「逆スケーラビリティ」(縮小社会における効率化)課題に直面する中、寺院も効率化しつつ伝統を維持する道を模索する必要があります。そうした中で、AIは単なる効率化ツールに留まらず、仏教の思想を未来に繋ぐ架け橋となる可能性を秘めています。
一方で、AIが人間の営みに深く入り込むほど、「AIに倫理や宗教観は必要か?」という根源的な問いも浮上します。ある僧侶は「むしろAIにこそ宗教が必要になるのではないか」と述べています。AIが発達し自律的に対話・判断するようになったとき、人々の幸福や善悪をどう捉えるかという基準づくりに宗教的価値観が寄与できるかもしれません。現時点でAIが悟りを開く境地に達することはありませんが、人間がAIを「育てる」上で仏教の知恵や倫理観を組み込むことは、技術と精神文化の新たな融合点となり得ます。
寺院におけるAI活用は、人間の役割を奪うものではなく解放するものです。雑事に追われていた僧侶がAIの助けで時間を作り、より多くの人々に寄り添い、智慧を届け、慈悲の実践に邁進できるならば、それは仏教本来の目的にも適うことでしょう。もちろん、テクノロジーの導入によって生じる弊害や違和感には丁寧に向き合い、伝統の良さと革新の利点をバランスよく取り入れていくことが重要です。AI時代の寺院は、古き良き精神性と最新技術とを併せ持つ、新たなコミュニティの核として進化していく可能性を秘めています。仏教が一貫して模索してきた「人が幸せになる道」に、AIという現代の知恵をどう融合させていくか——その挑戦は始まったばかりです (ブッダの説法とChatGPTが融合 仏教チャットボットその活用法は – DG Lab Haus)。今後の研究と実践を通じ、テクノロジーと宗教の調和した未来像が少しずつ形作られていくことでしょう。
参考資料:
寺院デジタル支援の366「おてらコール」発表 (寺院デジタル支援の366、電話/音声AIで高齢者の安否を確認する「おてらコール」をNTT東日本と共同開発 – AI Market) (寺院デジタル支援の366、電話/音声AIで高齢者の安否を確認する「おてらコール」をNTT東日本と共同開発 – AI Market)
朝日新聞デジタル「Robot helps spread Buddhist teachings…」 (Robot helps spread Buddhist teachings at a Kyoto temple | The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis) (Robot helps spread Buddhist teachings at a Kyoto temple | The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis)
同上(マインダーの説法システムに関する記述) (Robot helps spread Buddhist teachings at a Kyoto temple | The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis)
明治寺ブログ「人工説法」(ChatGPT生成の法話例) (人工説法 | ひとくち伝言) (人工説法 | ひとくち伝言)
マイナビニュース「お寺でAIは役に立ちますか?」前編(寺院のIT活用状況) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(7) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(前編) | TECH+(テックプラス)) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(7) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(前編) | TECH+(テックプラス))
同上 前編(寺院運営の効率化と課題) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(7) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(前編) | TECH+(テックプラス)) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(7) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(前編) | TECH+(テックプラス))
マイナビニュース「お寺でAIは役に立ちますか?」後編(善立寺のチャットボット事例) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(8) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(後編) | TECH+(テックプラス)) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(8) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(後編) | TECH+(テックプラス))
同上 後編(AIに宗教的倫理観が必要になる可能性) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(8) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(後編) | TECH+(テックプラス)) (知りたい! カナコさん 皆で話そうAIのコト(8) お寺でAIは役に立ちますか? – 浄土宗善立寺 副住職 こうじりゅうじ氏(後編) | TECH+(テックプラス))
The Medical AI Times「ロボット説教師は信仰心と寄付を失うか?」 (ロボット説教師は信仰心と寄付を失うか? | 医療とAIのニュース・最新記事 – The Medical AI Times)
同上(ロボット法話の信頼度と寄付額に関する実験結果) (ロボット説教師は信仰心と寄付を失うか? | 医療とAIのニュース・最新記事 – The Medical AI Times) (ロボット説教師は信仰心と寄付を失うか? | 医療とAIのニュース・最新記事 – The Medical AI Times)
お寺の日々#156(寺院IT化における検討項目) (◉お寺の日々#156 お寺におけるAI等の技術活用について|神崎修生@福岡県 信行寺) (◉お寺の日々#156 お寺におけるAI等の技術活用について|神崎修生@福岡県 信行寺)
同上(住職によるAI活用と逆スケーラビリティの話) (◉お寺の日々#156 お寺におけるAI等の技術活用について|神崎修生@福岡県 信行寺) (◉お寺の日々#156 お寺におけるAI等の技術活用について|神崎修生@福岡県 信行寺)
DG Lab Haus「ブッダの説法とChatGPTが融合…」 (ブッダの説法とChatGPTが融合 仏教チャットボットその活用法は – DG Lab Haus) (ブッダの説法とChatGPTが融合 仏教チャットボットその活用法は – DG Lab Haus)
高台寺ロボット観音マインダーの写真(朝日新聞) (Robot helps spread Buddhist teachings at a Kyoto temple | The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis)
ロイター通信「Robot monk blends science and Buddhism…」(中国・賢二の概要)
この記事を書いた人
DAISUKE YAJI
プロフィール
1999年3月 筑波大学第一学群自然学類数学科卒業
1999年4月 株式会社セブン&アイHD入社
2011年10月 株式会社セブン&アイHD退社
2011年11月 有限会社谷治新太郎商店入社
2012年12月 有限会社谷治新太郎商店代表取締役就任
2019年 カラーミーショップ大賞2019にて地域賞(東京都)
2020年 カラーミーショップ大賞2020にて優秀賞
2023年 ネットショップグランプリにて特別賞授賞
2024年 次世代コマース大賞にて大賞授賞
義父・義母・妻・長男・長女・次女・猫3匹の大所帯
趣味はゴルフ、月1回はラウンドしています。

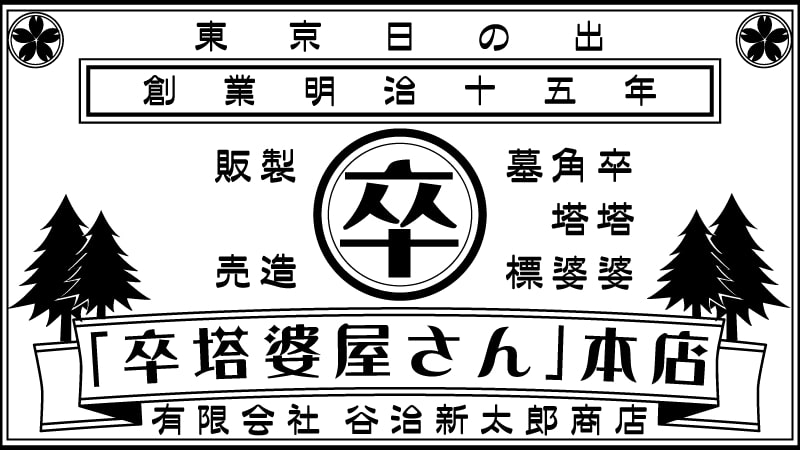








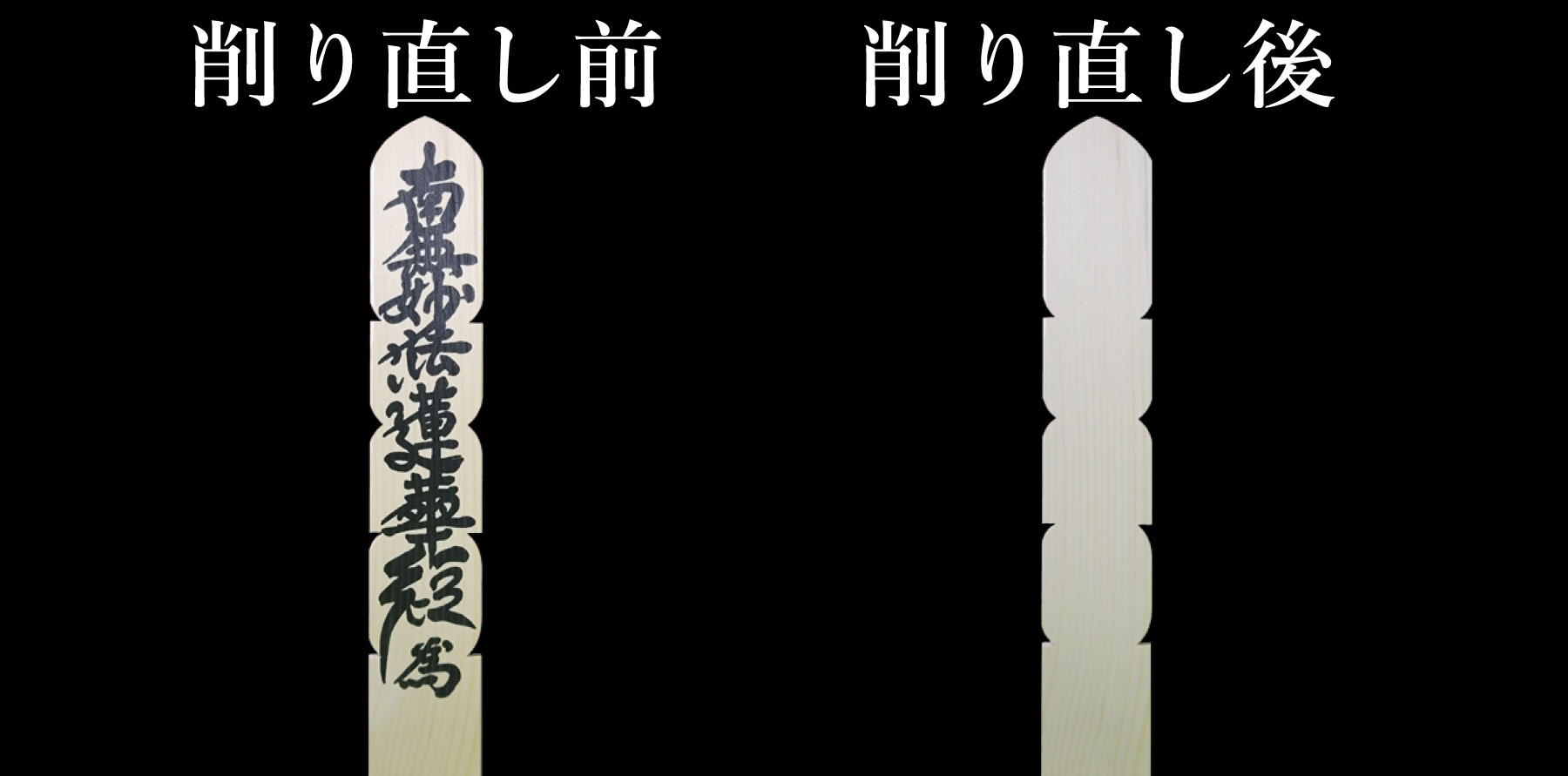






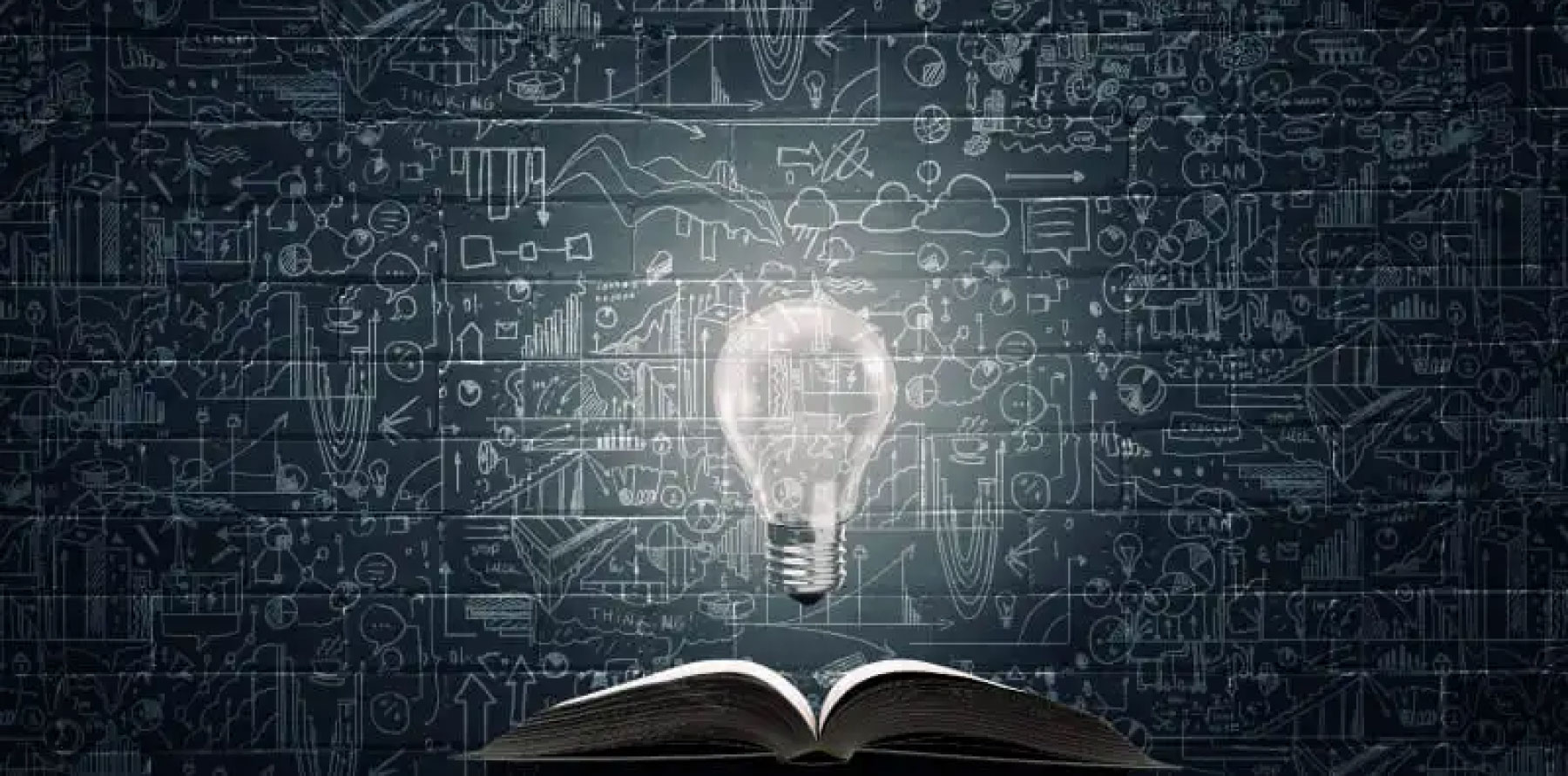

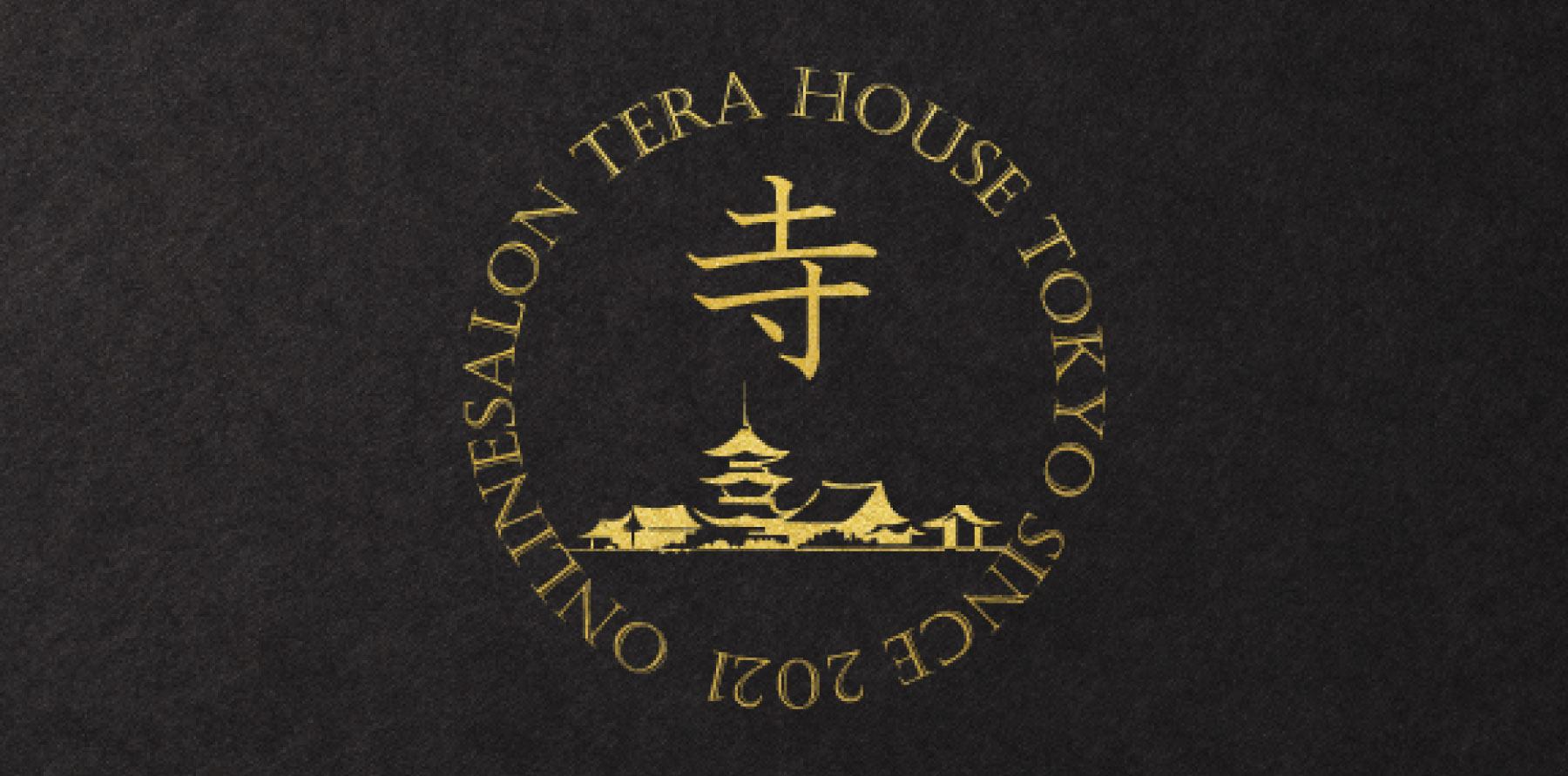
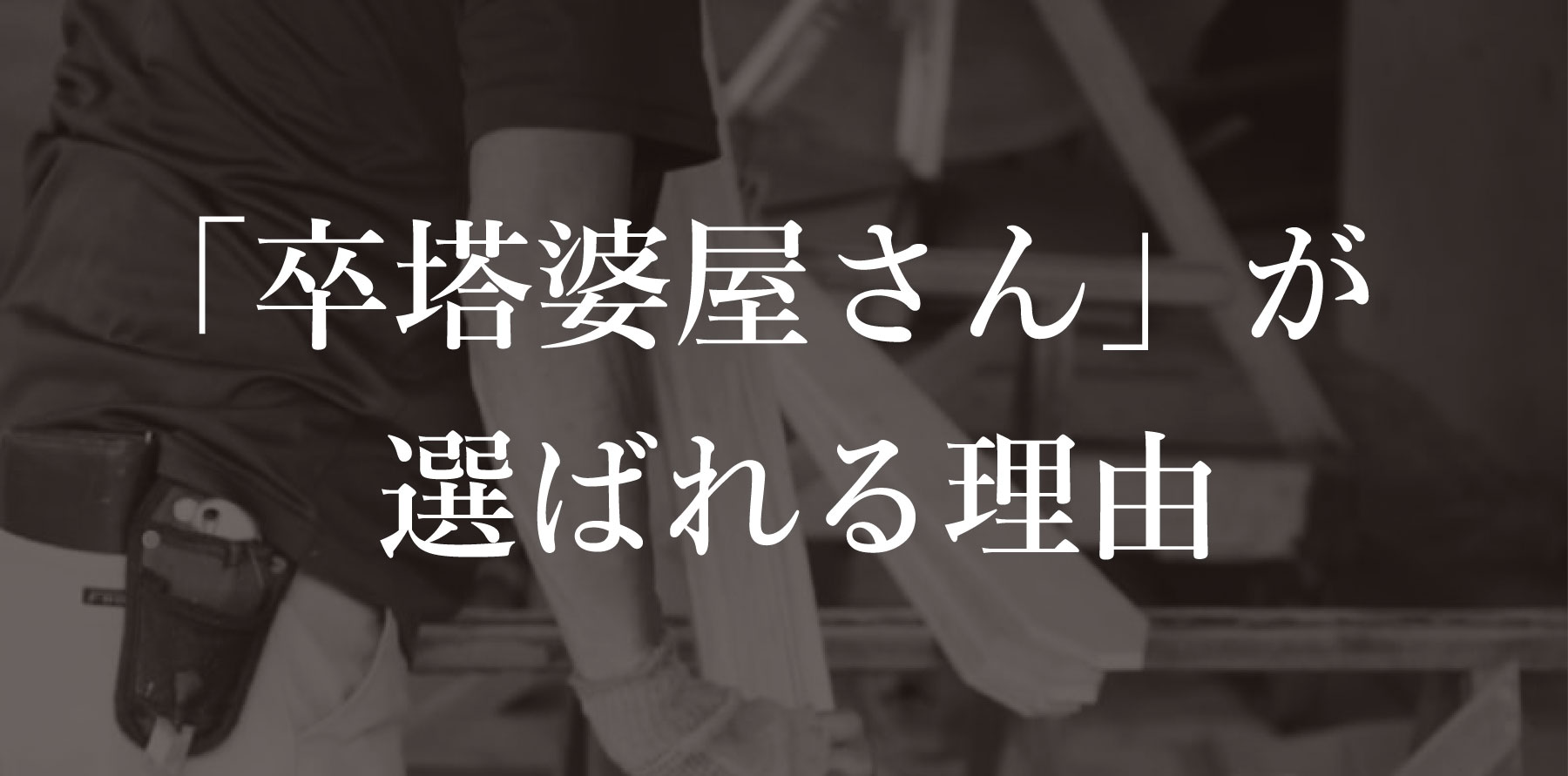
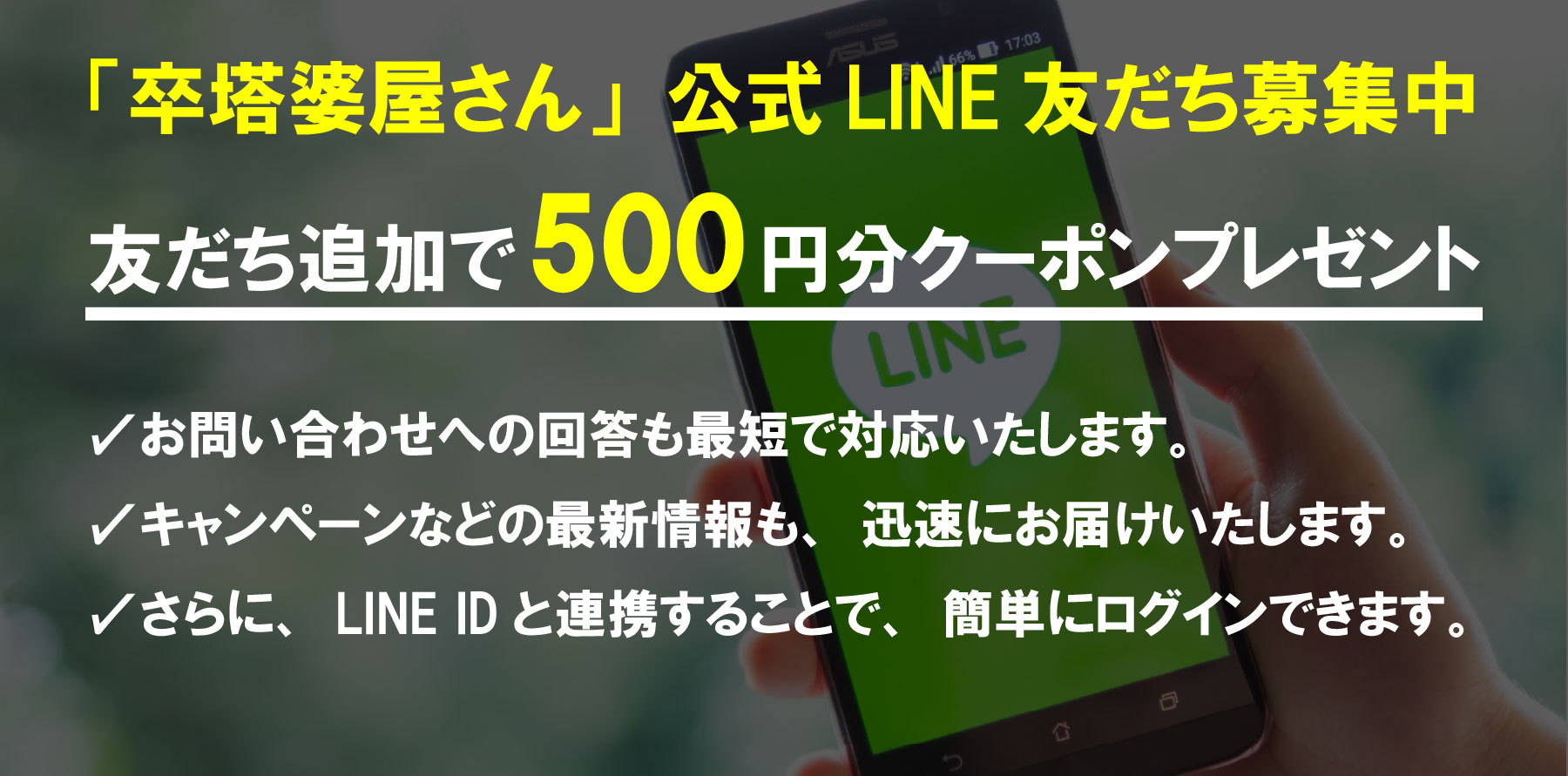


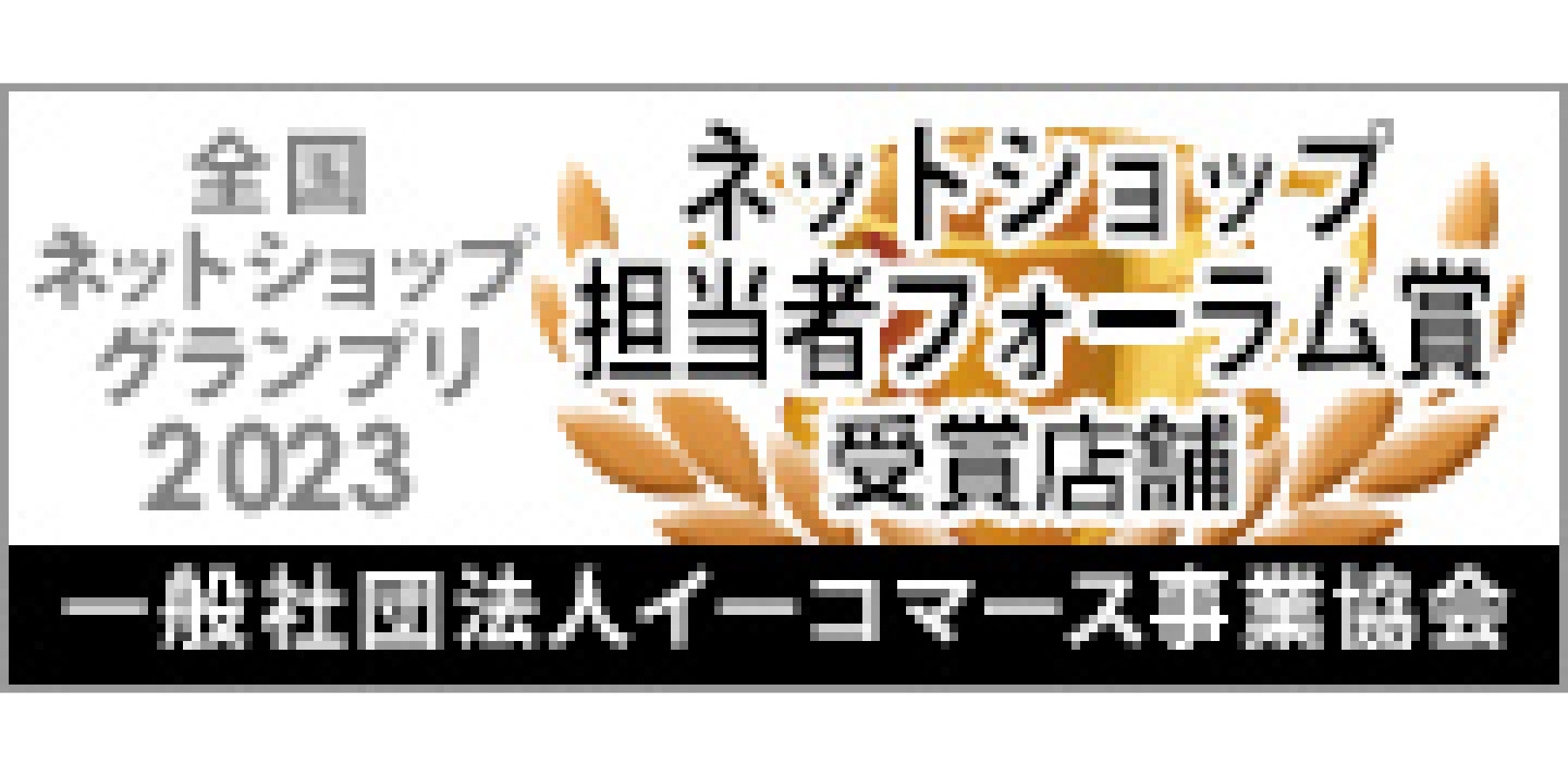




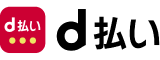





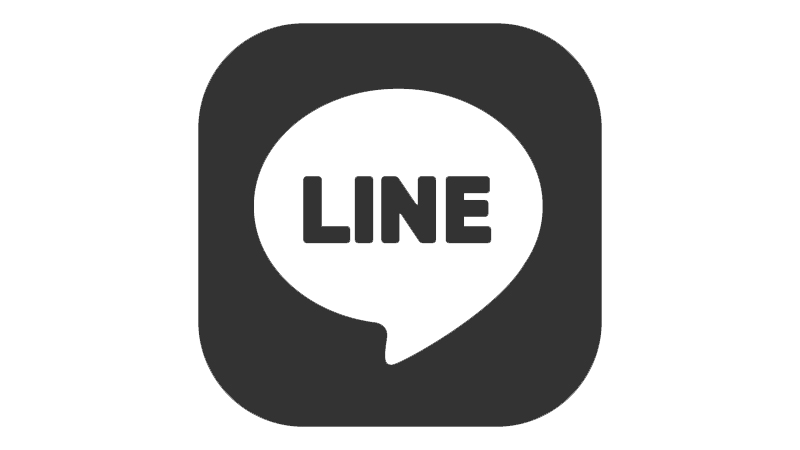
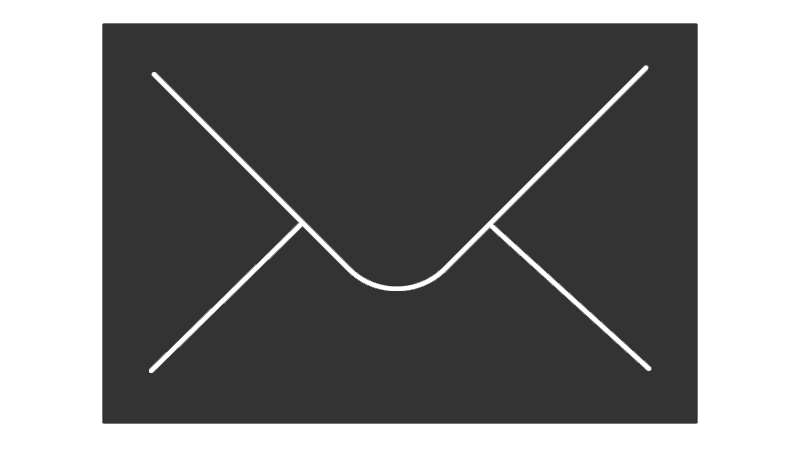

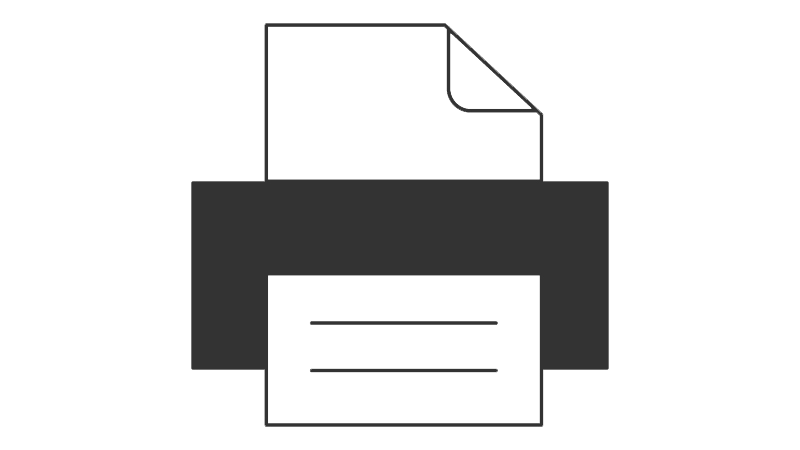
 卒塔婆(50本入)
卒塔婆(50本入) 卒塔婆(1本入)
卒塔婆(1本入)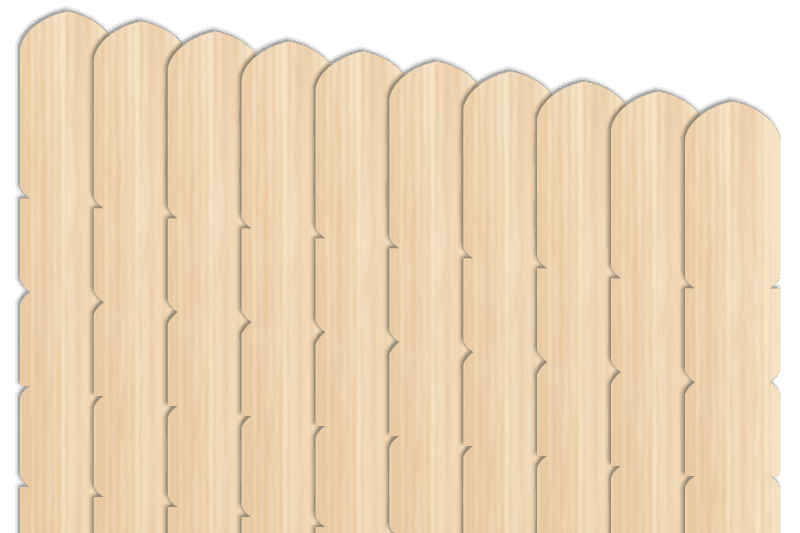 多摩産杉塔婆
多摩産杉塔婆 ECO卒塔婆
ECO卒塔婆 神式塔婆・祭標(50本入)
神式塔婆・祭標(50本入)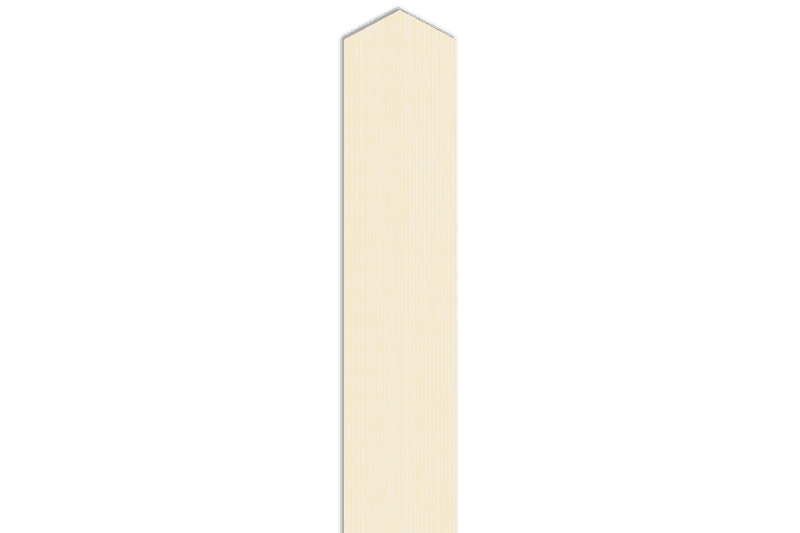 神式塔婆・祭標(1本入)
神式塔婆・祭標(1本入) 角塔婆(1本)
角塔婆(1本) 墓標(1本)
墓標(1本) 経木塔婆・水塔婆(200枚入)
経木塔婆・水塔婆(200枚入) 護摩木
護摩木